
西郷隆盛(1828年1月23日 – 1877年9月24日)は、日本の幕末から明治初期にかけての政治家、武士(薩摩藩士)であり、明治維新の中心人物の一人です。彼の名言には「我が身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」、「梅の花は寒い冬を耐え忍ぶ事で春に一番麗しく咲く」。
西郷隆盛のエピソード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1828年1月23日 |
| 死亡日 | 1877年9月24日 |
| 死因 | 自決 |
| 職業 | 政治家、軍人 |
| 活動期間 | 幕末から明治初期 |
| 主な功績 | 明治維新の一翼を担い、新政府の成立に貢献。西南戦争の指導者として知られる |
西郷隆盛(1828年1月23日 – 1877年9月24日)は、日本の幕末から明治初期にかけての政治家、武士(薩摩藩士)であり、明治維新の中心人物の一人です。彼の人生は、日本の近代化と変革の激動の時代を象徴しています。西郷の生涯は、薩摩藩の下級武士の家に生まれ、若い頃から藩の政治に関わり、幕末期の動乱に深く関与することになります。彼は尊王攘夷運動に影響を受け、外国の脅威に対抗するためには日本の統一と強化が必要であると考えました。西郷は坂本龍馬とともに薩長同盟の成立に大きな役割を果たし、この同盟は幕府に対抗する力となりました。また、勝海舟との間で江戸城の無血開城を交渉するなど、明治維新の平和的な進行に貢献しました。維新後、西郷は明治政府の要職に就き、版籍奉還や廃藩置県などの重要な政策を推進し、日本の近代国家への移行を支えました。しかし、政府内での意見の相違や、特に西南戦争における中央と地方の対立を巡る政策において、西郷は政府と対立する立場を取りました。この対立は、1877年の西南戦争へと繋がります。西郷は反乱を率いましたが、政府軍に敗れ、戦死しました。
薩長同盟の締結と大政奉還への影響

西郷隆盛は幕末の動乱期において薩摩藩と長州藩の間に薩長同盟を結ぶことに大きな役割を果たしました。この同盟は、徳川幕府に対抗するための重要な軍事同盟で、倒幕運動の一環として結ばれました。1866年に徳川幕府を武力倒幕するため軍事同盟で、中岡慎太郎が長州藩の桂小五郎を説得し、薩摩藩の西郷隆盛を坂本龍馬が説得した上で亀山社中が両者の問題を相互支援する形で取り持ち形になりました。その結果、犬猿の仲と言われていた薩摩藩と長州藩が同じ倒幕という道を歩み始めたきっかけにもなった同盟です。西郷隆盛は、当初、事態を静観していましたが、長州藩が危機的な状況に陥った時、薩摩藩は長州藩を支援することを決定しました。これは、坂本龍馬が提案したもので、薩摩藩が武器を購入し、それを長州藩に提供するというものでした。この提案により、長州藩は近代的な武器を入手することができ、幕府に対抗する力を得ることができました。薩長同盟は、幕末の日本における重要な出来事で、尊王攘夷派にとって大きな意義を持っていました。また、薩長同盟はその後の大政奉還にも影響を与えました。
坂本龍馬との関係

坂本龍馬との出会いはその後の日本の運命を大きく変えた出来事でした。1864年8月頃、西郷隆盛はすでに薩摩藩の顔役となっており、一方の坂本龍馬は勝海舟が設立した神戸海軍操練所の塾頭でした。この時、二人は勝海舟の紹介で出会い、その時の西郷隆盛の印象について、坂本龍馬は「釣鐘の例えると、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く。もし馬鹿なら大きな馬鹿で、利口なら大きな利口だろうと思います」と評価しています。その後、坂本龍馬は寺田屋遭難事件で手に刀傷を負い、その治療のために薩摩藩の藩船で鹿児島へと向かいました。この時、西郷隆盛は坂本龍馬を匿い、その治療を支援しました。この出会いとその後の交流は、西郷隆盛と坂本龍馬が新しい日本を創るために必要な人物として互いに頼り合う関係を築くきっかけとなりました。特に、寺田屋遭難事件で坂本龍馬が襲撃を受けたことにより、西郷隆盛は薩摩藩が幕府の敵となり、薩長による武力倒幕に反対していた薩摩藩の保守派を説得するしかないと決意しました。これが、薩長同盟の成立という歴史的な出来事へと繋がっていきます。
江戸城無血開城と勝海舟

1868年2月15日、東征大総督である西郷隆盛は京都を出発しました。当時、薩長両藩と会津藩との戦闘は、会津軍がオール徳川軍の一翼を担って江戸城の攻防戦に加わっていました。この戦いで徳川慶喜が降伏すれば、会津藩との戦闘もそれで終わる、会津藩の処分も慶喜の処分と一括で、ということであったであろう。その後、東征軍は3月12日と13日に池上本門寺、内藤新宿、板橋から江戸を包囲し、15日を総攻撃の日と決定しました。新政府の江戸総攻撃が迫っている中、勝海舟と山岡鉄舟が交渉をしようと計画を立てて、新政府と交渉するため奔走します。そして総攻撃が迫っている3月13日、西郷隆盛は山岡鉄舟の頑張りを見て、提示する7カ条にOKしてくれれば攻撃を中止しますという条件を提示します。しかし、山岡鉄舟はその内の1条「将軍・徳川慶喜を備前藩に預かりとすること」は断固拒否します。山岡鉄舟は西郷隆盛に「もし薩摩藩主をいきなり他の藩に預けるとなったら断固反対するだろ!」と問い詰めました。新政府は西郷隆盛の交渉を横目に順調に進んでいきます。そんな時新政府を戸惑わせるとんでもない事態が起きてしまいます。なんとイギリスが江戸総攻撃を中止しろと圧力をかけてきたのです。新政府はこの時ようやく江戸を攻撃したら日本は逆にとんでもないことになるということに気づいたのです。そして3月14日ついに幕府代表の勝海舟と新政府代表西郷隆盛が会談しました。新政府側の提案はなるべく徳川家に譲歩した内容でした。勝海舟はそれを受け入れました。勝海舟と西郷隆盛の交渉により、江戸城の無血開城が実現しました。これにより、人口150万人の大都市江戸での大規模な戦闘が回避され、多くの人々の命が救われました。
西南戦争と西郷隆盛の最後

西郷隆盛は、倒幕の指導者として、薩長同盟や戊辰戦争を遂行し、大久保利通・木戸孝允とともに、「維新の三傑」として高く評価されました。維新後は、新政府の参議・陸軍大将となりますが、征韓論を巡って大久保利通らと対立し、役職を辞任してしまいます。西郷は朝鮮侵略を行うことで国内の目を海外に向け反乱を防ぐことを主張しましたが、大久保利通らは国内改革を優先し、朝鮮への武力行使に反対しました。新政府との対立を深めた隆盛は、「西南戦争」で彼らと争うこととなるのです。西南戦争は征討軍(明治政府軍)と薩摩軍を合わせると、約130,000人もの人が戦闘に参加した大規模な乱でした。戦地は九州各地に及び、約半年の戦闘で両軍合わせて約13,000人の犠牲者を出しています。開戦から7か月、官軍死者6403人、薩軍死者6765人にのぼる最大の士族反乱は政府軍の勝利に終わり、西郷隆盛の切腹によって西南戦争は終結する事となりました。西南戦争が鎮圧されると、武力の限界性が明白となり、不平士族は自由民権運動へと合流していきました。武力での反抗として、特権を剥奪された士族の反乱が激しさを増しました。言論での反抗として、民衆参加の政治を求める自由民権運動が始まりました。
西郷隆盛の名言集(1)
名言1
何度も何度もつらく苦しい経験をしてこそ、人の志は初めて堅くなるのだ。
真の男は玉となって砕けることを本懐とし、志を曲げて瓦となって生き長らえることを恥とせよ。
我が家の遺訓。
それは子孫のために良い田を買わない、すなわち財産を残さないということだ。
名言2
過ちを改めるには、自分が間違いを犯したと自覚すれば、それでよい。
そのことをさっぱり思いすてて、ただちに一歩を踏み出すことが大事である。
過ちを犯したことを悔やんで、あれこれと取りつくろおうと心配するのは、たとえば茶碗を割って、そのかけらを集めて合わせてみるようなもので、何の役にも立たぬことである。
名言3
人が踏み行うべき道は、この天地のおのずからなる道理であるから、学問の道は敬天愛人(天を敬い人を愛する)を目的とし、自分の修養には、つねに己れに克つことを心がけねばならない。
己れに克つための極意は、論語にある「意なし、必なし、固なし、我なし」(主観だけで判断しない。無理押しをしない。固執しない。我を通さない)ということだ。
総じて人は自分に克つことによって成功し、自分を愛することによって失敗するものだ。
歴史上の人物をみるがよい。
事業を始める人が、その事業の七、八割まではうまくやるのであるが、残りの二、三割を終りまで成し遂げる人の少ないのは、はじめはよく己れを慎んで、事を慎重にするから成功もし、名も世に知られるようになる。
しかし、成功して名も知られるようになると、いつの間にか自分を愛する心が起こり、恐れ慎むという心が緩み、驕り高ぶる気持ちが多くなり、成功したことを自惚れて、何でもできるという過信のもとに、出来の悪い仕事をしてついに失敗する。
これはすべて自ら招いた結果である。
だから、自分にうち克って、人が見ていないときも聞いていないときも、慎み戒めることが大切なのだ。
名言4
西洋の刑法は、もっぱら戒めることを目的とし、むごい扱いを避け、善良に導くことに心を注ぐことが深い。
だから獄中の罪人であっても、緩やかに取り扱い、教戒となるような書籍を与え、場合によっては親族や友人の面会も許すということだ。
西洋のこのような点は誠に文明だと感じるものだ。
名言5
物事に取り組む際、自分の思慮の浅さを心配することはない。
およそ思慮というものは、黙って座り、静かに思いをめぐらしているときにすべきことである。
そのようにすれば、有事のときには、十のうち八、九は実行されるものだ。
事件に遭遇して、はじめて考えてみても、それは寝ているときに夢の中で奇策やすばらしい思いつきを得たとしても、朝起きたときには、役に立たない妄想のたぐいが多いのと同じである。
名言6
会計出納はすべての制度の基礎である。
国家事業はこれによって成り立ち、国家運営の最も重要なことであるから、慎重にしなければならない。
そのあらましを申すならば、収入をはかって支出をおさえるという以外に手段はない。
年間の収入によってすべての計画を定め、会計を管理する者が一身をかけて定まりを守り、予算を超過させてはならない。
そうでなくして時勢にまかせ、制限を緩慢にし、支出に合わせて収入をはかるなら、結局国民に重税を課するほか手はなくなるであろう。
もしそうなれば、一時的に事業は進んだように見えても、国力は疲弊して救い難いことになるだろう。
名言7
策略は日常的にすることではない。
はかりごとをめぐらしてやったことは、あとから見ると善くないことがはっきりしていて、必ず後悔するものである。
ただ戦争において策略は必要なことであるが、日常的にはかりごとをやっていると、いざ戦いということになったとき、同じことはできないだろう。
蜀漢の丞相であった諸葛孔明は、日頃策略を用いなかったから、戦いのときに思いもよらないはかりごとを行うことができたのだ。
私はかつて東京を引き揚げたとき、弟(従道)に対して、私はこれまで少しもはかりごとをやったことがないから、跡は少しも濁ることはないだろう。
それだけはよく見ておくようにと言いおいたことがある。
名言8
人が踏み行うべき道を実践しようとする者は、偉業を尊ばないものである。
北宋の司馬温公(司馬光)は、寝床で語る言葉さえ、人にいえないようなことはないといわれた。
独りを慎むということの真意はいかなるものであるかわかるであろう。
人の意表をつくようなことをして、一時的にいい気分に浸るのは、未熟者のすることで、戒めなければならないことだ。
名言9
賢人がすべての役人を統轄し、政権が一つの方針に進み、国の体制が一つにまとまらなければ、たとえ有能な人物を登用し、自由に進言できるようにして、多くの人の考えを取り入れるにしても、どれを取捨するのか一定の方針がなくては、行うことは雑でまとまりがなく、とても成功どころではない。
昨日出された政府の命令が、今日には変更になるというようなことも、統轄するところが一つでなく、政治の方針が決まっていないからである。
名言10
節操を貫き、道義を重んじ、心清らかで恥を知る心を持つ。
これを失うようなことがあれば、決して国家を維持することはできない。
上に立つ者が下の者に対して自分の利益を争い求め、正しい道を忘れるとき、下の者もみなこれにならい、人の心は財欲にはしり、日に日に卑しく、節義廉恥の志を失い、親子兄弟の間ですら財産を争い互いに敵視するようになるのだ。
このようになったら何をもって国を維持することができようか。
徳川氏は将兵の勇猛な心を抑えて世を治めたが、今の時代は昔の戦国時代の勇将よりもっと勇猛な心を奮い起さなければ、世界のあらゆる国々と対峙することはできないのだ。
普仏戦争の際、フランスが三十万の兵と三ケ月の食糧を残して降伏したのは、あまりにそろばん勘定にくわしかったがためである。


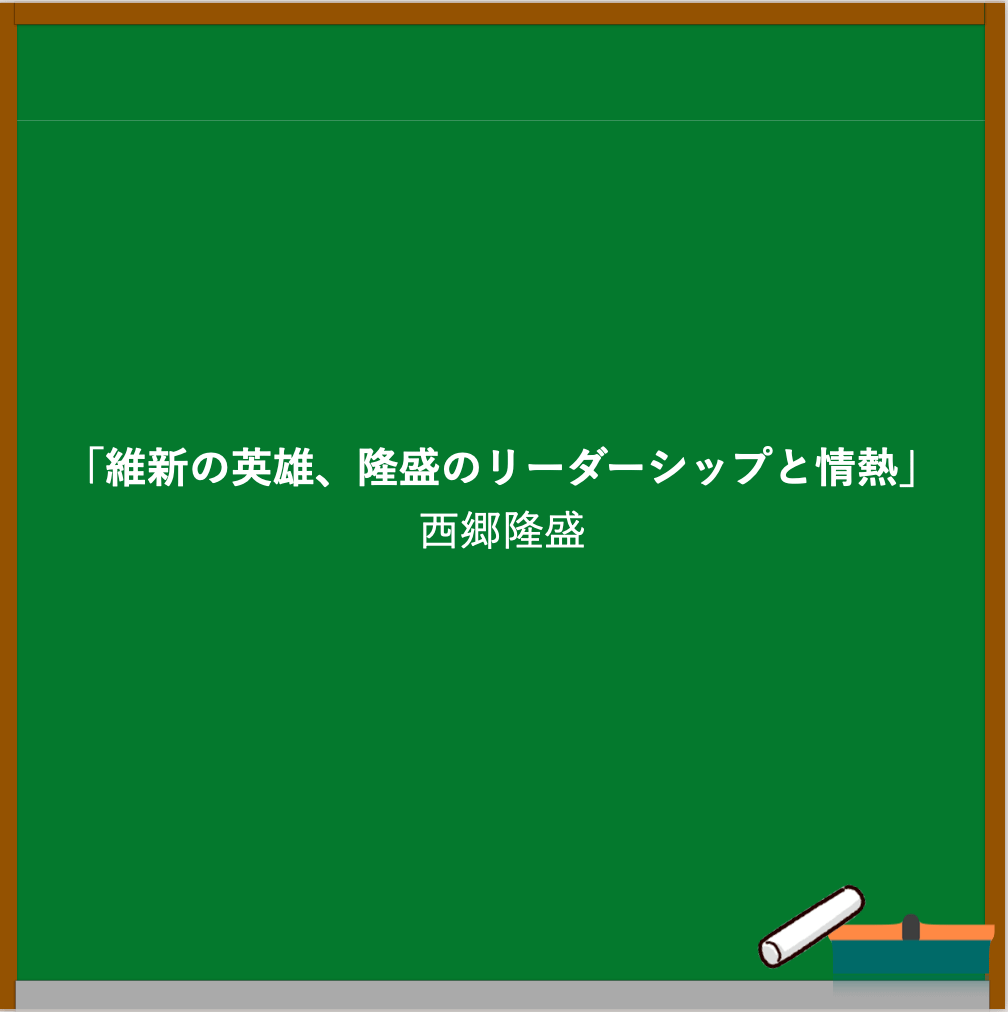





コメント