天下統一を目前とし「本能寺の変」にて衝撃の最後を遂げた織田信長氏。そんな彼は「信長の野望」や「仁~JIN~」など後世の作品にも度々登場する人気ぶりです。日本史初の天下統一を成し遂げた人物であり、その功績は現在の日本の礎となっております。彼はその身分による投与ではなく能力による家臣選定など革新的な運用でその領地を拡大していきました。彼の名言には、「必死に生きてこそ、その生涯は光を放つ。」、「是非に及ばず」などがあります。
織田信長ってどんな人?
天下統一後一歩までいったものの、本能寺の変で無念の死を遂げた織田信長はどのような人生を歩んだのでしょうか。その人物の人生を知ると名言にもより面白さが生まれます。彼の人生を幼少期と天下統一に分けて解説していきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1534年6月23日 |
| 死亡日 | 1582年6月21日 |
| 出身地 | 尾張国(現在の愛知県) |
| 主な業績 | 尾張一国の統一、桶狭間の戦いでの勝利、上洛と織田政権の確立 |
| 政策 | 「天下布武」の印の使用、鉄砲隊の結成、楽市楽座政策、関所の廃止 |
| 死因 | 自害(本能寺にて) |
織田信長の幼少期

「鳴かぬなら 殺してしえ ホトトギス」でお馴染みの織田信長はその破天荒なエピソードで知られています。その幼少期の逸話をいくつかまとめましたのでご覧ください。
赤ちゃんからヤンチャ
織田信長は1534年、尾張(現在の愛知県西部)の戦国大名、織田信秀の嫡男として生まれました。幼名は吉法師です。信長が生後まもなく乳母のもとで養育されるが、非常に疳の強い子で乳母の乳首をかみ破るため、何人もの乳母が交替したと言い伝えられています。
大うつけ者だが切腹で改心
若き日の信長が、「大うつけ」と呼ばれていたのは有名です。うつけとは、「まぬけ」や「バカ」といった意味です。信長の旧臣である太田牛一が書き残した「信長公記」によれば、信長は普段の生活に、入浴時に着る湯帷子を普段着にし、袖を脱ぎっぱなしにし、毛先をツンツンにしたまげ姿で町中をだらしなく歩いていたようです。また、有名なエピソードですが、父・信秀の葬儀に際しては、いつもの奇妙な格好で現れ、焼香を位牌に投げつけて帰ったのです。この行動に対して、教育係の平手政秀が信長を諫めるために切腹しました。この出来事により、信長は自身の行動を反省し態度を改めたと言います(諸説あり)。信長の性格がわかるエピソードを下記にまとめておりますので、ぜひご覧ください。
天下統一までの道のり
織田家の当主となった織田信長ですがそんな彼はどのようにして戦国の世を統治していったのでしょうか。そんな彼の生き様を紹介していきます。
桶狭間の戦い

1560年に行われたこの戦いでは、織田信長が今川義元を破りました。当時、今川義元は駿河、遠江、三河の3国(現在の静岡県と愛知県東部)を治める有力な戦国大名でした。しかし、尾張国(現在の愛知県西部)を治めていた信長が義元を破ったことは、当時の大名や武将たちに大きな影響を与えました。この戦闘は日本の歴史において、織田信長が台頭し、その後の統一への布石となった重要な出来事でした。
長篠の戦い

長篠の戦いは、1575年6月29日(ユリウス暦)、現在の愛知県新城市長篠で起こった戦いです。この戦いは、織田信長と徳川家康の連合軍と、武田勝頼率いる武田軍との間で行われました。武田勝頼は、父・武田信玄の死後、武田家を継ぎ、信玄の志を引き継ぎ、三河北部の重要拠点である長篠城を手に入れようとしました。しかし、長篠城の城主・奥平信昌は500名の兵で城を守り、家康の助けを待ちました。信長と家康の連合軍は、長篠城の近くの設楽原に陣を構えました。信長は、敵から見えないように兵を配置し、防御陣を構築しました。織田信長と徳川家康の連合軍は、設楽原に陣地を構築し、大量の鉄砲隊を配置して武田軍を待ち構えていたのです。一方、勝頼は、信長と家康の連合軍との戦いを控え、家臣の間で意見が分かれました。しかし、勝頼は、重臣たちが反対した、勝頼の側近たちの意見、「設楽原へ軍勢を動かし攻撃する」というものを選びました。設楽原への攻撃を決定し、主力の1万2千を設楽原に移動させました。この結果、織田・徳川の連合軍の鉄砲に包囲されその多くの兵を失います。信長と家康の連合軍は、長篠城を奪還し、戦いにも勝利しました。一方、勝頼は、信長や家康に連戦連勝していたという自信が裏目に出て、多くの家臣や兵を失いました。長篠の戦いの後、武田家の力は衰え、1582年に信長、家康、北条氏政らは、武田氏を滅ぼすために武田征伐を開始しました。追い詰められた勝頼は、武田家ゆかりの地、天目山で自らの命を絶ちました。
本能寺の変
本能寺の変は、1582年6月2日に起こった出来事で、明智光秀が謀反を起こし、京都の本能寺に滞在していた主君・織田信長を襲撃した事件です。信長は寝込みを襲われ、包囲されたことを悟ると、寺に火を放ち、自害して果てました。信長の嫡男で織田家当主の信忠も襲われ、宿泊していた妙覚寺から二条御新造に移って抗戦したが、やはり建物に火を放って自害しました。信長と信忠の死によって織田政権は瓦解しましたが、光秀もまた6月13日の山崎の戦いで羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に敗れて命を落としました。この事件は秀吉が台頭して豊臣政権を構築する契機となり、戦国乱世は終焉に向かいました。光秀が謀反を起こした理由については、定説が存在せず、多種多様な説があります。また、信長と信忠の遺体が見つからなかったこと、京都の混乱終結に手間取ったこと、秀吉の中国大返しなど、光秀が3つの誤算を犯したとも言われています。
名言「是非に及ばず」
「是非に及ばず」は、織田信長が本能寺の変の際に述べたとされる言葉です。この言葉は、現代では「物事の良し悪しややり方などを議論する必要が無かったり、もはやそのようにするような段階ではない場合」を表す言葉として使われています。つまり、「どうにもならなかったり、やむを得なかったり、仕方がなかったりするようなこと」を表します。本能寺の変が起きた際、織田信長は家臣にいかなるものの仕業かと問われ、明智光秀の仕業であると知らされ、その際に「是非に及ばず」と述べたと伝えられています。この言葉には大きく二つの解釈があります。
- 「やむを得ない」という諦めの意味:信長が明智光秀に襲撃され、周囲を囲まれた時にはすでに時遅しという状況下でした。つまり「今からいくら反戦しても勝ち目はない、無理である」というところから、「諦めるしかない」「仕方がない」「やむを得ない」という意味で使われたという解釈です。
- 「逆境を乗り越えよう」という積極的な意思:「あれこれと迷っている場合ではない。今すぐ行動を起こそう」という意味があり、不遇な状況で前向きな意思を表す言葉としても解釈ができます。「とにかく逆境を乗り越えよう」という積極的な意思のもとで、信長がこの言葉を放ったという解釈です。
このように、「是非に及ばず」の解釈は人により異なり、その真意については現在でも様々な議論が続いています。しかし、どちらの解釈にせよ、この言葉は織田信長の強い意志と決断力を象徴していると言えるでしょう。それは、彼の生き方や指導力を反映しており、今日でも多くの人々に影響を与えています。
織田信長の家臣たち
織田信長の家臣として有名な、秀吉と家康について簡単に紹介します。彼らの優秀な働きがあったからこそ信長の天下があったといっても過言ではありません。
豊臣秀吉
秀吉は、尾張国愛知郡中村郷で足軽の子という低い身分に生まれました。しかし、織田信長の下で手柄を挙げ、地位を手に入れ、本能寺の変後には天下人にまでなりました。彼は人心掌握術に長けた性格で、人がやりたがらない仕事を進んで引き受けたり、人に対して物腰柔らかに接したり、時には盛大にお金を使って人々の心を掴み出世していったのです。秀吉について詳しく知りたい方は次の記事を参照ください。
徳川家康
徳川家康と織田信長の間で、永禄5年(1562年)に清洲同盟が結ばれました。この時から天正10年(1582年)に「本能寺の変」で信長が亡くなるまでの20年間、両者は同盟関係を継続していました。しかし、最初は対等であったはずの同盟関係は、いつからか家康が下の従属関係に変化していきました。家康はどこまでも忍耐強く現実的な人物でした。彼は慎重で現実的な性格で、苛烈で果断に富んだ織田信長や、人好きがして立ち回り上手だった豊臣秀吉とはまた違い、家康はどこまでも忍耐強く現実的な人物でした。家康について詳しく知りたい方は次の記事を参照ください。
織田信長の名言集(1)
名言1
是非に及ばず
(しかたがない。やむを得ない)
名言2
器用というのは他人の思惑の逆をする者だ。
名言3
仕事は探してやるものだ。
自分が創り出すものだ。
与えられた仕事だけをやるのは雑兵だ。
名言4
攻撃を一点に集約せよ、無駄な事はするな。
名言5
臆病者の目には、敵は常に大軍に見える。
名言6
恃(たの)むところにある者は、恃むもののために滅びる。
名言7
理想を持ち、信念に生きよ。
理想や信念を見失った者は、戦う前から負けているといえよう。
そのような者は廃人と同じだ。
名言8
およそ勝負は時の運によるもので、計画して勝てるものではない。
功名は武士の本意とはいっても、そのあり方によるものだ。
いまその方の功名は軽率な動きである。
一方の大将となろうとする者は、そのような功名を願ってはならぬ。
身の危ういのをかえりみないのは、それほど手柄と言うことはできない。
今後はこの心を忘れるな。
名言9
人を用ふるの者は、能否を択ぶべし、何ぞ新故を論ぜん。
名言10
愚かな間違いを犯したらたとえ生きて帰ってきてもワシの目の前に姿を見せるな。


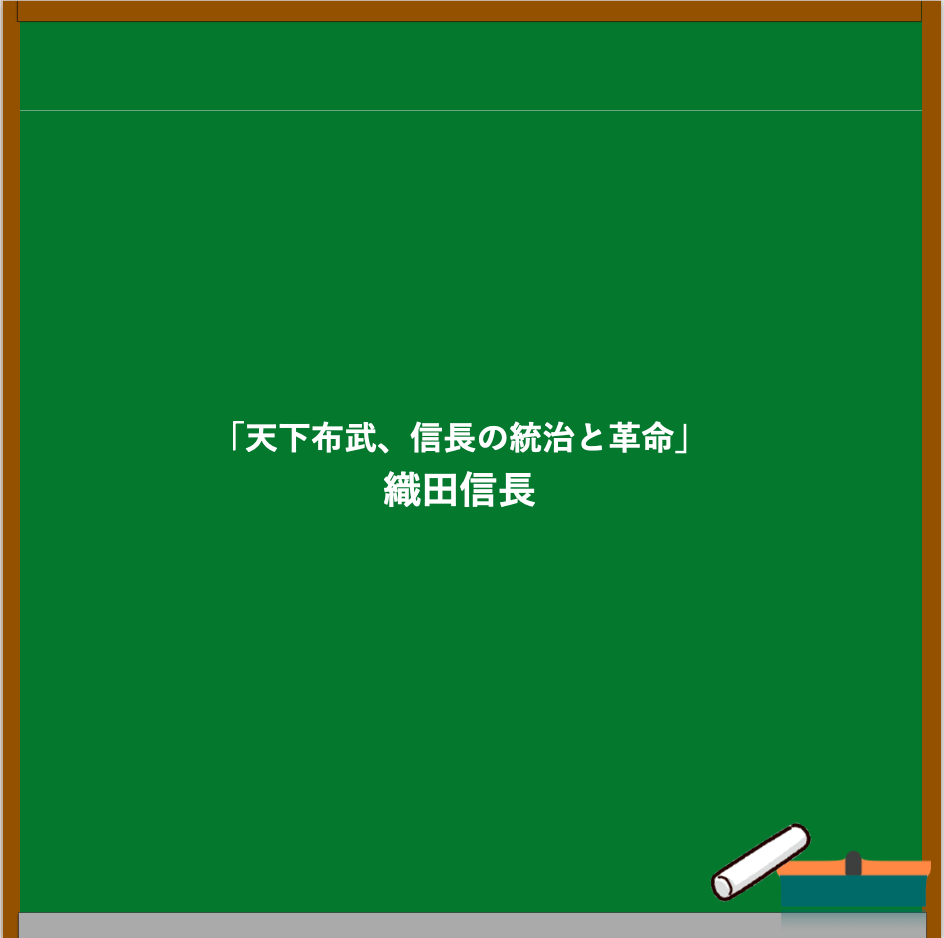





コメント