
武田信玄は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将であり、甲斐源氏の第19代当主、武田氏の第16代当主として知られています。彼の言葉は、時代を超越し、今日でも私たちに深い洞察と啓示を与えています。彼の名言には、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。」、「勝敗は六分か七分勝てば良い。八分の勝ちはすでに危険であり、九分、十分の勝ちは大敗を招く下地となる。」、「一生懸命だと、知恵が出る。 中途半端だと、愚痴が出る。 いい加減だと、言い訳が出る。」などがあります。
武田信玄のってどんな人?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1521年12月1日 |
| 死亡日 | 1573年5月13日 |
| 出身地 | 甲斐国(現在の山梨県) |
| 主な業績 | 甲斐一国の統一、川中島の戦い、上洛と武田政権の確立 |
| 政策 | 「風林火山」の印の使用、騎馬隊の結成、兵農分離政策、関所の設置 |
武田信玄は、1521年に甲斐の国(現在の山梨県)で生まれた日本戦国時代を代表する武将です。彼は武田信虎の息子として生まれ、若い頃からその非凡な才能を示しました。20歳で父を追放し家督を継ぎ、武田家を統率すると、その政治手腕と軍事戦略で甲斐を超えた地域への影響力を急速に拡大していきました。信玄の治世は、信濃国への侵攻をはじめとする積極的な領土拡大政策により特徴づけられます。彼の軍は、川中島での上杉謙信との伝説的な五度にわたる合戦を含む、数多くの戦いに勝利しました。これらの合戦では、彼の軍略が最大の強みとなり、特に「風林火山」という軍旗に示される戦術は今日でも広く知られています。政治面では、信玄は「甲州法度之次第」と呼ばれる一連の法律を制定し、その統治下で経済と社会の安定を図りました。これらの政策は、彼の領土内での強力な基盤を確立するのに役立ちました。武田信玄はまた、騎馬軍団の効果的な使用や兵站術の専門知識を通じて、軍事戦略の面でも革新をもたらしました。彼の指揮下での武田軍は、補給線の確保と迅速な移動を可能にすることで、長期間にわたる戦闘でも高い戦闘力を維持することができました。
父親の追放と家督の継承
武田信玄(当時は晴信)が20歳の時、彼は父・信虎を追放し、武田家の家督を継ぎました。この出来事は、信玄が家督を継ぐための異例の形で行われました。信虎が駿河国に向かった際、信玄は重臣の協力を得て、信虎を甲斐国から追い出しました。この時、信玄は「兵を送り駿河との国境を封鎖せよ」と命じ、信虎を帰国できないように駿河に追放しました。この一連の出来事は、信玄が21歳の時に起こりました。信虎を追放した理由については諸説あります。一つは、親子不仲説です。信虎と信玄の間には溝があり、この溝は結局埋まることはありませんでした。信虎は元旦に信玄には盃を与えずに、弟の信繁に盃を与えました。これはどう見ても「当主の座は弟に渡す」という信虎のあからさまな態度であり、このようなことが重なって信玄が父の追放を決意したという説があります。もう一つの説は、領国経営失敗説です。信虎は隣国と戦い続けていたため、経済封鎖を受けてしまいました。それが原因で甲斐の国は飢餓や物価の高騰で悩まされていました。そのため聡明な信玄は「このままでは武田家内に内乱が起きてしまう」と考え、「民衆を助けるため」という大義名分のもと、父を駿河に追放して国を変えようとしたというのが、信虎追放の真相だと考えられています。追放された信虎は駿河で隠居生活を送ることになり、信玄は父の生活費などについて今川義元と協議し、不自由がないように手配もしました。逆に子供に追放された信虎は激しい気性ゆえ、怒りが収まらなかったとされています。信虎は甲斐へ戻ろうとしたが、その願いは通じずに追放から33年後の77歳で死去しました。
武田信玄の騎馬隊(風林火山)

武田信玄が率いた騎馬隊は、戦国時代の日本において特筆すべき軍事力の一翼を担っていました。彼の騎馬隊は、その高度な機動力と衝撃力を活かした戦術で知られ、甲斐の国(現在の山梨県)を中心に、信濃(現在の長野県)などへの軍事行動において重要な役割を果たしました。特に、「風林火山」という戦術指南に基づき、風のように素早く、林のように静かに、火のように攻撃的で、山のように動じない姿勢を騎馬隊に要求しました。この指針に従い、武田信玄の騎馬隊は多くの戦いでその威力を発揮しました。信玄の騎馬隊は、戦場での急襲や敵陣への突撃、そして敵の動きを封じるための迅速な動きを得意としていました。また、騎馬隊の効果的な運用は、優れた兵站と補給体系によって支えられていたことも特徴です。これにより、遠征や長期にわたる戦闘でも、騎馬隊の戦闘能力を維持することができました。信玄の下で、騎馬隊は多くの合戦でその真価を発揮し、特に川中島の戦いでは上杉謙信の軍と何度も激突しました。これらの戦いでは、双方の騎馬隊が重要な役割を果たし、戦国時代の戦術や戦闘の様式に大きな影響を与えました。
上杉謙信との戦い(川中島の戦い)
川中島の戦いは、戦国時代に甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名である武田信玄と、越後国(現在の新潟県)の戦国大名である上杉謙信との間で行われた一連の戦闘を指します。この戦いは、主に信濃国(現在の長野県)の川中島で行われ、1553年から1564年までの12年間にわたり5度に渡って繰り広げられました。
第一次合戦(1553年): この戦いは、武田信玄が信濃国に侵攻し、信濃の国衆の本領復帰のために立ち上がった上杉謙信との間で起きました。しかし、この戦いでは明確な勝敗はつきませんでした。
第二次合戦(1555年): 上杉謙信は自ら川中島に兵を進め、出陣してきた武田軍と衝突しました。しかし、この戦いでも明確な勝敗はつきませんでした。
第三次合戦(1557年): 信玄が先に兵を進め、川中島周辺にある上杉方の城を攻略し始めました。しかし、この戦いでも決戦には至らず、双方とも撤退しました。
第四次合戦(1561年): この戦いは最も大規模な戦闘が行われ、双方ともに数千人もの死者を出しました。しかし、武田信玄の右腕である弟の武田信繁や軍師の山本勘助などが戦死しました。また、この戦いでは上杉謙信が武田信玄と一騎討ちを行ったとされています。
第五次合戦(1564年): この戦いでも双方は塩崎城を境に布陣しましたが、特に武田信玄側は決戦を避け、二ヶ月もの間、お互いにらみ合いを続けました。
これらの戦いで明確な勝者は出ませんでしたが、武田信玄は川中島を武田領にすることに成功しました。しかし、越後侵略は諦めざるを得ませんでした。
武田信玄の名言集(1)
名言1
人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。
名言2
勝敗は六分か七分勝てば良い。
八分の勝ちはすでに危険であり、九分、十分の勝ちは大敗を招く下地となる。
名言3
いくら厳しい規則を作って、家臣に強制しても、大将がわがままな振る舞いをしていたのでは、規則などあってなきがごとしである。
人に規則を守らせるには、まず自身の言動を反省し、非があれば直ちに改める姿勢を強く持たねばならない。
名言4
渋柿は渋柿として使え。
継木をして甘くすることなど小細工である。
名言5
人間にとって学問は、木の枝に繁る葉と同じだ。
名言6
信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ。
名言7
晴信(信玄)の弓矢は欲のためではなく、民百姓を安楽にするためだと民に知らせれば、わしが軍を進めるのを待ち望むようになる。
名言8
三度ものをいって三度言葉の変わる人間は、嘘をつく人間である。
名言9
もう一押しこそ慎重になれ。
名言10
晴信(信玄)が定めや法度以下において、違反しているようなことがあったなれば、身分の高い低いを問わず、目安(投書)をもって申すべし。
時と場合によって自らその覚悟をする。


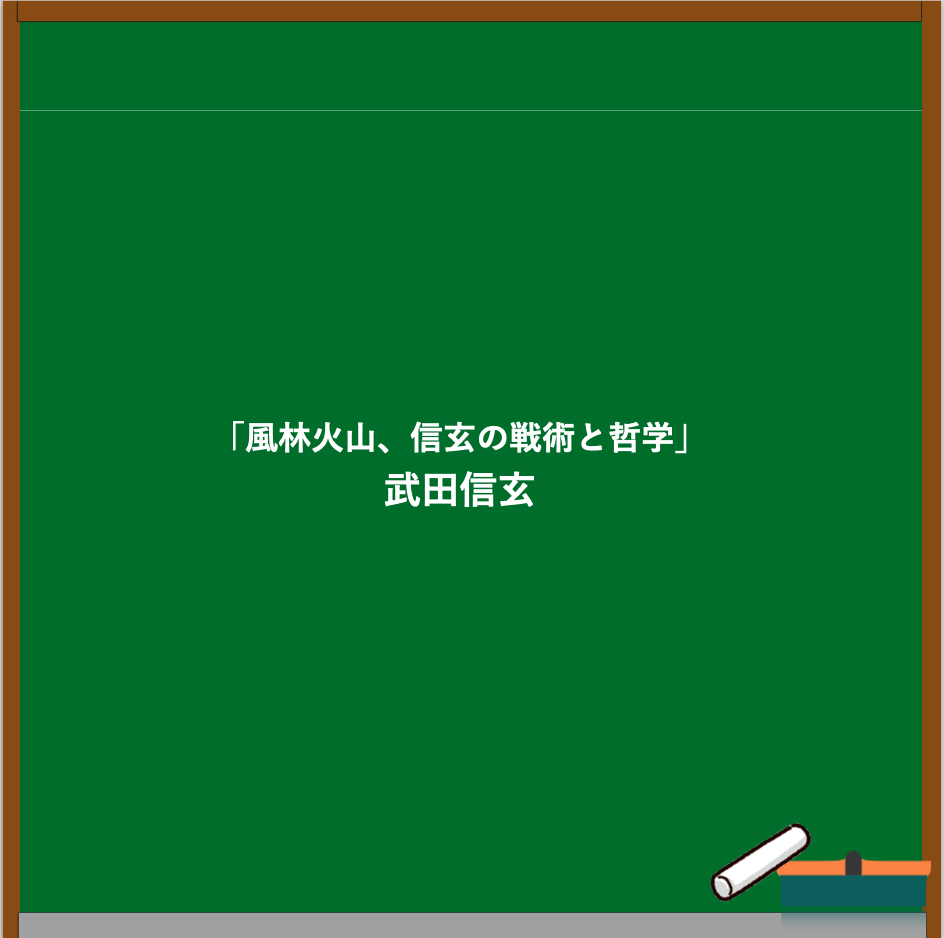


コメント