
毎年耳にする芥川賞、そんな偉大な賞の名前にもなっている芥川龍之介は日本文学のまさに巨匠と呼ばれるに相応しいでしょう。「羅生門」など、現代でもその名作具合に驚かされ、たびたび小学校の演劇でも取り上げられます。そんな彼は古典文学をオマージュした作風と、人間の醜い部分を克明に描く筆力を持ち味としており、多くの名作を残しました。容姿も淡麗で女性には困らないと思いきや、意外と繊細で心配性な一面をのぞかせるエピソードもあります。彼の名言からそんな彼の内面を探っていきましょう。
芥川龍之介ってどんな人?
容姿端麗かつ圧倒的な表現力とカリスマ性を持った天才作家であり、後世の作家たちに多大なる影響を与えた人物です。あの太宰治も憧れ、芥川賞の受賞を懇願するほどだったと言われています。しかし、そんな彼も一文学者であり、自身の繊細な内面を小説だけではなく時には女性に向けていることもありました。彼を象徴するエピソードを引用しどんな人物であるかの理解を深めていきましょう。
芥川龍之介のプロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1892年3月1日 |
| 出生地 | 東京府東京市京橋区(現在の東京都中央区) |
| 両親 | 新原敏三、フク |
| 職業 | 小説家 |
| 主な作品 | 『羅生門』、『鼻』、『今昔物語集』、『宇治拾遺物語』、『蜘蛛の糸』 |
| 死亡日 | 1927年7月24日(35歳) |
芥川龍之介の作風
芥川龍之介は、大正時代から昭和初期にかけて活躍した小説家で、短編小説の名手として知られています。彼の作風は、古典文学をオマージュした作風と、人間の醜い部分を克明に描く筆力を持ち味としています。『今昔物語集』『宇治拾遺物語』などのエピソードを、現代的に翻案した作品を数多く残しています。また、話の筋が分かりやすく、教育的な児童小説も残していて、特に『羅生門』『蜘蛛の糸』あたりは、現在でも教科書などの教育現場で親しまれています。教育的で芸術至上主義的な作品や、人間が生きていくうえで、必ず付きまとってくる苦悩、あるいは人のエゴイズムや欲望を主題とした作品を、その鋭敏な感性と教養をもって数多く残しました。芥川の作品はしばしば社会と個人の関係に焦点を当て、その複雑な相互作用を探求しています。彼は社会的な要因が個人の運命や行動に与える影響を明らかにし、個人の内面と社会の矛盾に深く洞察しました。例えば、「鼻」では、主人公の鼻の異常が社会的地位に及ぼす影響を風刺的に描写し、社会の虚栄心と個人の欲望の対立を浮き彫りにしています。芥川の作風は、当時の流行であった、理想的かつ個人主義的な「白樺派」と対極に位置する「新現実主義文学」として、人々から親しまれました。芥川の文章構成の方法は英文学的、という声もあります。これらの特徴から、芥川龍之介の作風は、人間の本質を、繊細な文章と物語によって描いたものと言えます。
芥川龍之介の性格
芥川龍之介は、繊細で自信がなく、厭世的な側面を持つ一方で、活発で人当たりの良い性格も持っていました。彼の性格は、彼の複雑な生い立ちと交友関係によって形成されました。彼は幼少期を伯母のフキのもとで過ごし、その教育熱心な環境の中で、頭の良い子として成長しました。しかし、生後7ヶ月頃に母親が精神に異常をきたし、母親の実家に預けられるという経験は、彼に深い影響を与えました。これにより、彼は「頑張らねば見捨てられてしまう」という強迫観念に突き動かされるように生きることとなりました。また、芥川は夏目漱石を師と仰ぎ、漱石の「木曜会」に学生時代から参加していました。この会合では、若手文学者たちがさまざまな議論を行い、芥川もその一員として活躍しました。特に、作家仲間で特に仲がよかったのが菊池寛で、彼との交友関係は芥川の人格形成に大きな影響を与えました。しかし、芥川の性格には神経質で悲観的な側面もあり、晩年には厭世的な思考も目立ちました。彼の作品からもその人となりや思想は伝わってきます。繊細で自信がなく、厭世的でさえあった芥川。しかし、その心の傷口から生まれてきたのが芥川が世に残した名作の数々であったのかもしれません。
いけない恋!?禁断の不倫関係
文豪として当然のように妻がありながら愛人を持った芥川龍之介。
彼は妻に宛てた遺書の中で堂々と不倫について打ち明けています。
大事件だったのは僕が二十九歳の時に秀夫人と罪を犯したことである。僕は罪を犯したことに良心の呵責は感じていない。唯相手を選ばなかった為に(秀夫人の利己主義や動物的本能は実に甚しいものである。)僕の生存に不利を生じたことを少からず後悔している。
「遺書/芥川龍之介」
小説家なら妄想であってくれ!と妻は願ったでしょうね笑
残念ながらこの不倫は事実であり、芥川龍之介自身にも非常に深いトラウマを植え付けたようです。
意外にも長編小説は書けない!?
芥川賞と聞けば皆が長編小説を思い浮かべるかもしれませんね。でも実は全くそんなことがなく、中編、短編に送られる賞であることをご存知でしょうか?
なんとその理由は彼が長編小説を書くと登場人物の性格が支離滅裂になってしまったからです。笑
登場人物全員が多重人格は確かに大変ですね汗
小説家といえば長編小説のイメージが強いですが、意外にもそんなことはなく得意不得意があったのですね。
芥川龍之介の名言集(1)
名言1
道徳は常に古着である。
名言2
恋愛はただ性欲の詩的表現を受けたものである。
少なくても詩的表現を受けない性欲は恋愛と呼ぶに値しない。
名言3
われわれを恋愛から救うものは、理性よりもむしろ多忙である。
名言4
他人を弁護するよりも自己を弁護するのは困難である。
疑うものは弁護士を見よ。
名言5
軍人の誇りとするものは、小児の玩具に似ている。
なぜ軍人は酒にも酔わずに、勲章を下げて歩かれるのであろう。
名言6
恋愛の徴候の一つは彼女に似た顔を発見することに極度に鋭敏になることである。
名言7
わたしは二三の友だちにはたとい真実を言わないにもせよ、嘘をついたことは一度もなかった。
彼等もまた嘘をつかなかったら。
名言8
打ちおろすハンマーのリズムを聞け。
あのリズムが在する限り、芸術は永遠に滅びないであろう。
名言9
正義は武器に似たものである。
武器は金を出しさえすれば、敵にも味方にも買われるであろう。
正義も理屈さえつけさえすれば、敵にも味方にも買われるものである。
名言10
私は不幸にも知っている。
時には嘘によるほかは語られぬ真実もあることを。


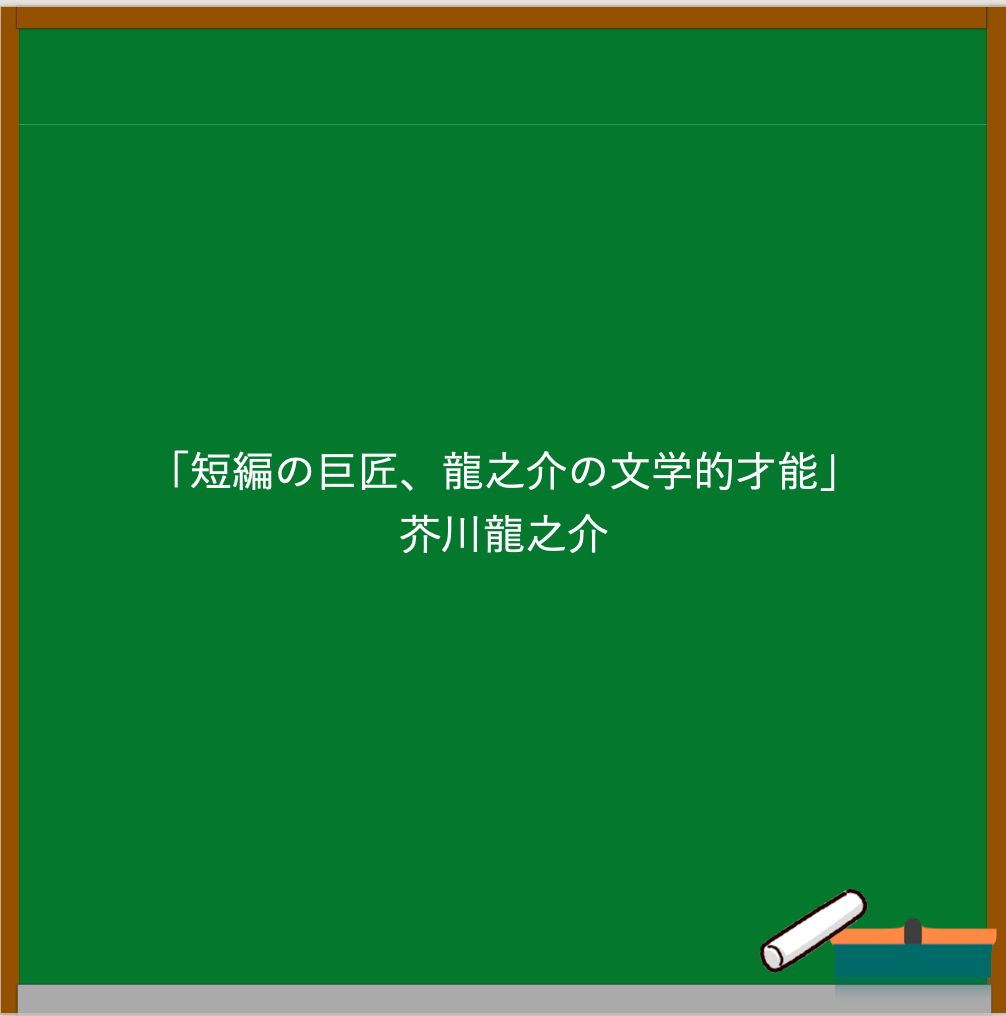


コメント