
スティーブン・スピルバーグは、多くの名作を生み出し、その才能と独創性で世界中の人々を魅了してきました彼の名言には、「映画に行くといつも、それは魔法のように心を引きつけ、夢中にさせる。どんな映画であってもね。」、「僕の悩みの種はイマジネーションが止まらないことなんだ。朝起きても気持ちが高ぶって朝食が食べられない。エネルギーが尽きてしまうこともない。」などがあります。
スティーヴン・スピルバーグって何がすごい?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1946年12月18日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ |
| 職業 | 映画監督、映画プロデューサー |
| 主な作品 | ジョーズ、ジュラシック・パーク |
| 受賞歴 | SF名誉の殿堂入り |
スティーブン・スピルバーグは、1946年12月18日にアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティでウクライナ系ユダヤ人の家庭に生まれました。彼は、映画監督兼映画プロデューサーとして知られています。彼は「アメリカで最も裕福なセレブリティ」第2位になるほど人気で実力のある映画監督です。2018年には映画監督として総興行収入が100億ドルを突破したことで有名です。彼は、1969年から多くの作品を制作し、その中でもジョーズやジュラシック・パークなどが有名です。彼は、文学作品以外でSF名誉の殿堂入りも達成しています。彼の少年時代には、ユニバーサル・ハリウッドで伝説的なエピソードを残しています。彼は17歳の頃、ユニバーサル・スタジオの見学ツアーが開催されていた時に、トイレに隠れてツアーバスが過ぎ去るのを待ちました。そして、関係者に見つかると、通行証を貰うことに成功しました。この通行証を貰ってからは、色々な人と関わりを持つことができました。ここで広げた人脈や経験が後々彼の作品を作る上で大切な基盤になっています。
革新的な映画製作
スピルバーグは、革新的な技術と物語を映画に取り入れることで知られています。彼の映画は、観客に未知の体験を提供し、映画製作における新たな可能性を切り開きました。特に「ジョーズ」は、サマーブロックバスターの概念を生み出し、世界中での大ヒットとなりました。この作品は、観客を緊張の糸で繋ぎ止める革新的なサウンドトラックと特殊効果で、映画史に新たな一章を刻みました。
多様なジャンルへの挑戦
スピルバーグは、冒険、SF、戦争、ファンタジーなど、さまざまなジャンルの映画を手掛けてきました。彼の多様な作品リストは、彼がいかに幅広い視野を持ち、異なるジャンルに挑戦し続けているかを物語っています。「インディ・ジョーンズ」シリーズでは、アクションと冒険の魅力を最大限に引き出し、一方で「A.I.」では、人間とテクノロジーの関係を深く掘り下げました。
代表作品映画
スティーブン・スピルバーグは数多くの名作を生み出していますが、その中でも特に代表的な作品をいくつか選び、それぞれのあらすじを簡単に紹介します。
ジョーズ (1975)
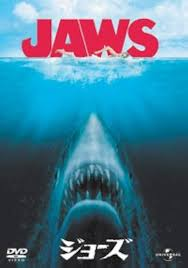
美しい海辺の小さな町アミティに突如現れた巨大な人食いサメによる恐怖が描かれます。町の保安官ブロディは、サメ退治のために海洋学者とサメハンターを連れて緊迫の対決に挑みます。スピルバーグはこの作品で、独特の緊張感と恐怖を観客に味わわせ、サマーブロックバスターの先駆けとなりました。
E.T. (1982)

地球に取り残された小さな宇宙人E.T.と、彼をかくまう少年エリオットとの友情を描いた作品です。E.T.はエリオットと心を通わせ、彼の家族との絆も深まりますが、やがて政府の手によって捕らえられてしまいます。エリオットと友人たちは、E.T.を宇宙船に送り返すための壮大な計画を実行に移します。この映画は、家族愛と友情の普遍的なメッセージで世界中を感動させました。
ジュラシック・パーク (1993)
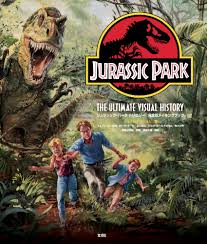
遺伝子操作によって恐竜が蘇ったテーマパークを舞台にした冒険映画です。パークのプレビューツアーに招かれた一行は、恐竜たちが生き生きと暮らす光景に驚愕しますが、システムの故障により恐竜たちが脱走し、島は恐怖に包まれます。スピルバーグは、革新的なCGIと実物大のアニマトロニクスを駆使して、恐竜と人間の息をのむような対決をリアルに描き出しました。
スティーヴン・スピルバーグの名言集(1)
名言1
映画に行くといつも、それは魔法のように心を引きつけ、夢中にさせる。
どんな映画であってもね。
名言2
僕の悩みの種はイマジネーションが止まらないことなんだ。
朝起きても気持ちが高ぶって朝食が食べられない。
エネルギーが尽きてしまうこともない。
名言3
映画監督の視点から言えば、キャスティングは才能やスキルよりも運命や宿命ということもある。
名言4
僕は年齢を重ねても、決して年を取らない。
それがハングリー精神を維持する秘訣だ。
名言5
映画検閲と良識と倫理的責任との間には微妙な違いしかない。
名言6
僕たちは皆、毎年毎年違う人間なんだ。
一生を通じて同じ人間なんてことはない。
名言7
映画の撮影前、僕は常に4つの映画を見る。
それは『七人の侍』、『アラビアのロレンス』、『素晴らしき哉、人生!』、『捜索者』になることが多い。
名言8
オードリーは自分が手にした以上のものを与えてくれた。
彼女に会えなくなって、全世界が寂しがるよ。
名言9
自分の映画を夢見てはいけない。
作るのだ!
名言10
その世代の読者が、その世代の作家を生み出す。


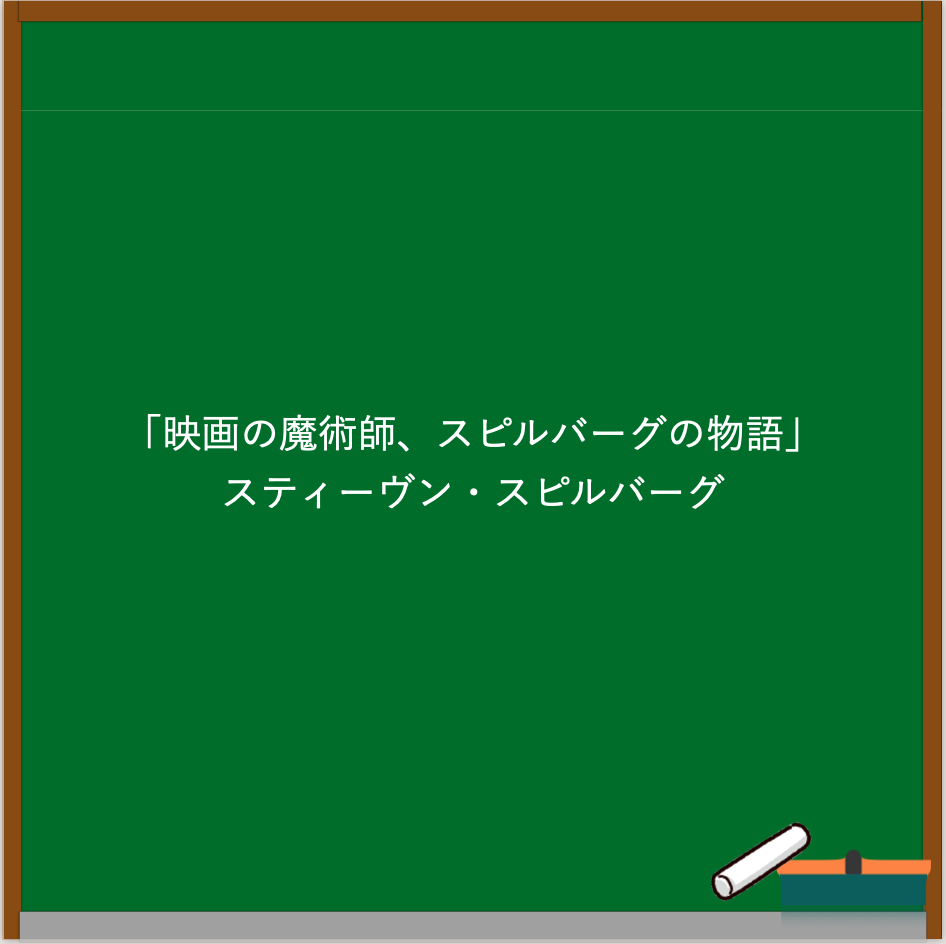


コメント