
みんな大好きキングダム、そして三国志といえばお馴染みこの人、諸葛亮孔明ですよね!その思慮の深い戦略から、何度も窮地を脱し形成を逆転し、その名を大陸に轟かせました。そんな彼の名言に、「優れた人は静かに身を修め、徳を養なう」、「才に傲りてもって人に驕らず、寵をもって威を作さず。」があります。優れた人はただ何も言わずに能力を付け、時を待つことが大切ということですね。さらには能力に驕らず、常に人に謙虚であるべきであるということですね。あんなに大胆な諸葛亮孔明でさえ、その影には血の滲むような努力があったことが窺えます。
諸葛孔明ってどんな人?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 諸葛孔明 |
| 生年 | 西暦181年 |
| 出身地 | 山東省 |
| 主な役職 | 軍師将軍、左将軍、丞相 |
| 主な業績 | 劉備との出会い、赤壁の戦いでの勝利、蜀の国力回復、魏への5回の侵攻 |
| 死因 | 過労死(諸説あり) |
| 死亡年 | 西暦234年 |
諸葛孔明は三国志の時代に活躍した英知と策略で知られる軍師であり、実務に長けた政治家でもありました。181年に山東省で生まれ、青年期は勉学に励む日々を過ごしました。207年、劉備との出会いが彼の運命を大きく変えました。劉備は孔明の才能を見込んで彼を家臣として迎え、赤壁の戦いでの大勝やその後の蜀の統治において、孔明の策略や知略が大きく影響しました。劉備の死後、孔明は蜀の丞相として国を支え、五度の北伐を行いながらも漢の再興を目指しましたが、234年に病に倒れ、途中でその生涯を閉じました。彼の生涯は後世に多くの物語や映画、文学作品の題材となり、今もその名は多くの人々に愛されています。
三国志の時代の力関係
この時代は、それぞれの国が中国全土を統一しようとし、様々な軍事的、政治的な駆け引きが行われた時期でした。
- 魏:曹操によって建国され、その後、曹丕によって漢の皇帝を廃位させてから魏の皇帝となりました。魏は北中国を中心に強大な力を持っていました。
- 呉:孫権が率いる南中国の勢力で、赤壁の戦いで曹操の大軍を撃退したことで知られています。
- 蜀:劉備が建国した国で、蜀漢とも呼ばれます。山岳地帯に位置し、領土は比較的狭いが、諸葛亮のような優秀な人材に恵まれていました。
諸葛孔明の逸話11選
諸葛孔明の逸話1(三顧の礼)
劉備が諸葛孔明の才能を聞きつけ、彼を迎え入れるべく訪ねる逸話です。しかし、最初の2回は孔明が家におらず、会うことができませんでした。劉備は諦めずに3度目の訪問を試み、この時ようやく孔明と会うことができました。劉備のこの熱意を見た孔明は感激し、劉備のもとで仕事をすることを決意しました。
諸葛孔明の逸話2(空城の計)
魏の司馬懿が大軍を率いて孔明の拠点である城を攻めてきた際、孔明は城の門を大きく開けて自ら門上に座り、琴を弾くという策を用いました。司馬懿はこれを見て孔明の罠を疑い、攻撃を中止して撤退しました。実際には孔明の軍は大きな損害を受けており、戦力的には劣勢でしたが、この策によって一時的に敵を退けることができました。
諸葛孔明の逸話3(草船借箭)
孔明は呉との連合軍で曹操軍との赤壁の戦いに挑む際、矢が不足していることに悩んでいました。そこで彼は敵から矢を借りるという策を思いつきます。霧の中、軍を編成して曹操軍の近くまで進出。その船には藁人形を立て、敵に矢を放たせました。曹操軍は藁人形に向けて大量の矢を放ち、孔明はこれを回収して矢の不足を解消しました。
諸葛孔明の逸話4(牛の油で火攻め)
こちらも逸話3でご紹介した赤壁の戦いでの逸話になります。諸葛孔明は曹操軍の船団に対する火攻めを計画しました。まずは火攻めの準備として、彼は大量の牛の油を用意しました。諸葛孔明は、牛の油を敵船に投げつけることで、炎が広がる速度を速め、敵船を一瞬で炎上させることを企んでいたのです。諸葛孔明の計画通り、火攻めが実行され、曹操軍の船団は瞬く間に炎上しました。これにより、曹操軍は大混乱に陥り、諸葛孔明の軍は大勝利を収めました。
諸葛孔明の逸話5(泣いて馬謖を斬る)
「泣いて馬謖を斬る」とは、諸葛孔明が自らの部下である馬謖を処刑するエピソードです。馬謖は軍事的な失策を犯し、重要な地位を失うことになります。諸葛孔明は馬謖の才能を高く評価していましたが、軍律を遵守する必要があり、泣きながら彼を処刑する決断を下します。この話は、リーダーシップと責任、法と情の間の葛藤を象徴的に表しています。
諸葛孔明の逸話6(錦嚢の計)
錦嚢の計(きんのうのけい)は、諸葛亮孔明の策略の一つです。この策略は、劉備が呉の孫権の妹との縁談のために呉に赴く際、その護衛を任された趙雲に孔明が3つの袋を渡し、特定のタイミングで袋を開けるように指示したものです。袋を開けると、孔明からの指示書が入っており、その指示に従い行動すると、立ちはだかる困難を次々と乗り越え、無事に劉備を護衛できたという話です。具体的には、孔明が事前に趙雲に渡しておいた錦嚢の計により、周瑜の立てた劉備暗殺計画が流れてしまいます。また、孔明の策略により、劉備は新妻孫夫人と共に無事に荊州に帰還することができました。
諸葛孔明の逸話7(水魚の交わり)
「水魚の交わり」は、水と魚のように、切っても切り離せない非常に親密な関係を表す言葉です。この言葉は、中国の『蜀書 諸葛亮伝』を原典とする故事成語で、『三国志演義』の中に出て来る逸話としても親しまれています。この言葉が生まれた背景には、劉備と諸葛孔明の間柄があります。劉備は三顧の礼を持って諸葛孔明を家臣に迎え、その後二人は親交を深めました。劉備は孔明に対して昼夜問わず意見を頼り、師として仰ぐ姿を劉備家臣は面白くなく劉備にうかがいました。それに対して劉備は、「孔明は水で、私は魚だ」と答えました。
諸葛孔明の逸話8(七縦七擒)
諸葛孔明の南征は、中国の三国時代に蜀の丞相であった諸葛孔明が、南方の反乱を鎮圧するために行った戦争です。この戦争で最も有名なエピソードは、敵将である孟獲を7度捕らえては7度放すという「七縦七擒」の逸話です。孟獲は南蛮の首領で、蜀に反抗的な態度を示していました。諸葛孔明は孟獲を捕らえることで南蛮の反乱を鎮圧しようとしましたが、孟獲は何度捕らえられても反抗的な態度を改めませんでした。そこで諸葛孔明は、孟獲を捕らえては放すという策略を繰り返し、孟獲の心を徐々に軟化させました。7度目に孟獲が捕らえられたとき、ついに彼は諸葛孔明の行動に感動し、蜀に帰順することを誓いました。これにより、南蛮の反乱は鎮圧され、蜀の安定が図られました。
諸葛孔明の逸話9(死せる孔明、生ける仲達を走らす)
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」は、中国の三国時代の故事に由来する言葉です。ここでの「孔明」は蜀の諸葛亮孔明、「仲達」は魏の司馬仲達を指します。この故事は、蜀と魏が五丈原で対陣している最中に諸葛亮孔明が病死し、蜀軍が撤退しようとしたところから始まります。これを聞いた司馬仲達はただちに追撃を開始しましたが、蜀軍が反撃の構えを示したため、仲達は孔明がまだ死んでおらず、何か策略があるのではないかと疑い、急いで撤退しました。この出来事から、「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という言葉が生まれ、すぐれた人物は、死後にも生前の威力が保たれていて、生きている者を恐れさせることのたとえとして使われるようになりました。
諸葛孔明の逸話10(白眉)
「白眉」は、多くの中で最も優れている人や物を指す言葉です。その由来は中国の『蜀書(馬良伝)』の故事にあります。この故事によれば、三国時代の中国の一国・蜀に、優秀な5人の兄弟がおり、その中でも最も優れた四男・馬良の眉に白毛が混じっていたとされています。このエピソードが転じて「白眉」は「数ある中で最も優秀な人・物」という意味になりました。ちなみにこの5兄弟の中には上でも紹介した馬謖もいます。
諸葛孔明の逸話11(出師の表)
「出師の表」は、中国三国時代の蜀の丞相、諸葛亮孔明が魏を討伐するために出陣する際、主君である劉禅に奉じた上奏文です。この文書は、孔明が自身の忠義と決意を表明し、また、国家の危機を説明するもので、その美しい文体と感動的な内容から、古来より「これを読んで涙を流さないものは忠臣にあらず」と言われるほど高く評価されています。具体的には、孔明は先帝劉備が天下統一の大業を達成する前に亡くなり、今、天下が三国に分かれ、蜀の地益州が疲弊していると述べ、現在が危急存亡の時であることを強調します。また、皇帝の側に仕える臣下たちは怠慢なく、忠義に生きる者たちは自己を犠牲にして仕えていると述べ、これは先帝から受けた恩義を劉禅に報いようとするものであると説明します。さらに、孔明は郭攸之、董允、費禕、向寵などの賢臣を推薦し、人を用いるときは偏りなく、賞罰は公平に行うべきであると劉禅に教えます。そして、後漢が衰退した原因を説明し、劉禅に警告します。自身が北伐の決意を述べ、もし北伐が成功しなければ自らも処罰すると誓います。
幼少期に両親が他界
諸葛孔明は181年に現在の山東省にあたる徐州で生まれました。父親は郡の副長官を務めていましたが、孔明が幼少期に母親は亡くなり、父もその後を追うように孔明が8歳の時に死んでしまいます。両親を亡くした孔明は叔父の諸葛玄に弟と一緒に引き取られ、その後、荊州(けいしゅう)に移り住みます。しかし叔父も孔明が17歳の時に反乱に敗れ命を落としてしまいます。弟と2人で生きていくこととなった孔明は、荊州が学問が盛んであったこともあり、勉学に力を入れるようになります。このように、諸葛孔明の幼少期は両親を早くに亡くし、叔父に引き取られるという困難な状況でしたが、それでも彼は学問に励み、後の三国時代の英雄となる基礎を築きました。
諸葛孔明の最後(死因)
彼の死因に関しては、具体的な病名や詳細な状況が史書に詳細に記述されているわけではありませんが、一般的には、234年、五丈原(現在の陝西省)での北伐の軍事作戦中に、疲労や過労が原因で亡くなったとされています。彼が五丈原での戦役中に病気や体調不良になり、これが彼の死の直接的な原因となったと考えられています。しかし、諸葛亮孔明の死因やその詳細については、異なる解釈や推測も存在するため、彼の死に関する真実は完全には明らかになっていないとも言えるでしょう。
諸葛孔明の妻
諸葛孔明の妻は、通常は黄氏と呼ばれます。彼女の名前は一般的に「黄月英」または「黄婉貞」として知られていますが、これらは実名ではなく史書に名前が残っていません。彼女は荊州の名士であった黄承彦の娘で、見た目は美人ではなかったようですが、父親の言った通りの利発な女性で、内助の功で孔明を支えたと言います。彼女には発明家としての才能があったとも言われています。また、彼女の父親の黄承彦の妻は、荊州の豪族であり荊州の刺史であった劉表に仕えていた蔡瑁の長女でした。したがって、黄承彦の娘を嫁にもらうということは、劉表とは義理の叔父・甥の関係になるということです。これは孔明にとって重要なことであったに違いありません。
諸葛孔明の名言集(1)
名言1
天下は一人の天下にあらず、すなわち天下の人の天下である。
名言2
将帥、勇ならざるは、将なきに同じ。
名言3
それ必勝の術、合変の形は機にあり。
名言4
人の心をつかめる人は、敵を消滅できる。
古来、兵は戦を好まない。
名言5
それ用兵の道は、人の和にあり。
名言6
勢力や権力を目的とした交際は、長続きさせることが困難である。
名言7
学ぶことで才能は開花する。
志がなければ、学問の完成はない。
名言8
優れた人は静かに身を修め、徳を養なう。
名言9
自分の心は秤のようなものである。
人の都合で上下したりはしない。
名言10
才に傲りてもって人に驕らず、寵をもって威を作さず。


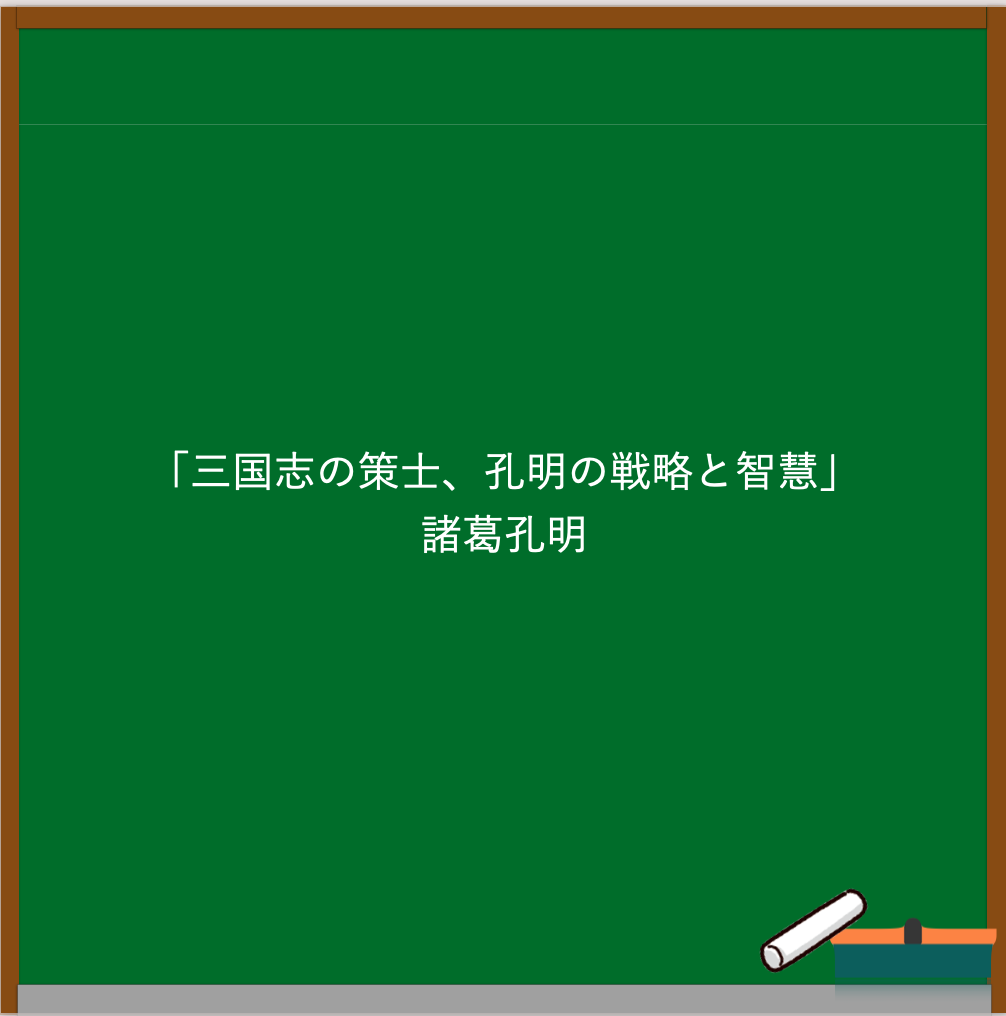


コメント