孔子は、紀元前551年頃に生まれた中国の思想家で、儒教の創始者とされています。彼の教えは、人間関係や政治、倫理など様々な分野に影響を与え、今でも多くの人々に愛されています。彼の名言には、「良心に照らして少しもやましいところがなければ、何を悩むことがあろうか。何を恐れることがあろうか。」、「己達せんと欲して人を達せしむ」 , 「四十にして惑わ図、五十にして天命を知る」などがあります。孔子の名言には、人生の指針となるものがたくさんあります。このブログでは、孔子の名言を紹介し、その意味や背景について考察していきます。
孔子とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 紀元前552年(または紀元前551年) |
| 死因 | 老衰(諸説あり) |
| 出身地 | 魯国、現在の山東省曲阜市 |
| 父親 | 70歳を超えた軍人戦士 |
| 母親 | 身分の低い16歳の巫女 |
| 弟子数 | 3000人 |
| 創始した教え | 儒教 |
| 儒教の徳 | 仁、義、礼、智、信 |
| 儒教の目的 | 「五倫」(父子、君臣、夫婦、長幼、朋友)を維持すること |
| 政治思想 | 徳治主義 |
孔子は紀元前552年(または紀元前551年)に魯国、現在の山東省曲阜市に生まれました。父親は既に70歳を超えていた軍人戦士、母親は身分の低い16歳の巫女であったとされます。孔子が3歳のときに父親は他界してしまいました。孔子は幼い頃から苦労して学を修めて、政治では大成しなかったが、弟子3000人から尊敬される大先生になりました。孔子は頭頂部がへこんでいて、2メートル越えの高身長で、食にこだわりがありました。孔子の創始した儒教は、「仁、義、礼、智、信」という5つの徳を大切にする教えであります。儒教の創始者である孔子。孔子が生きた時代の春秋時代末期は、周王朝が衰退して、有力者が覇権を争っていました。争いによって世の中は混乱し、権力者の専横が通って、政治も荒廃していました。そこで、孔子は徳のある統治者がその持ち前の徳をもって人民を治めるべきであるという、「徳治主義」を打ち出しました。法令や刑罰で厳しく取り締まったり、不必要に重い税を課したり、軍隊によって力づくで押さえつけて民を統治するのではなく、統治者の仁徳や礼によって民を導くのが正しい政治とされました。儒教にでてくる、仁と礼が政治では大切とされていたんですね。
孔子の教え
孔子の教えを理解するために、彼の思想を現代の日常生活に置き換えてみましょう。まず、「仁」と「礼」は、孔子の教えの中心的な概念です。「仁」は人を愛することを基本とし、「礼」は外見的な秩序を意味します。孔子は「人徳によって政治を行えば、星々に慕われる北極星となる」と説きました。これは、リーダーが道徳的な価値を持つことで、他の人々から尊敬され、信頼されるという考え方です。また、「君子は器にあらず」という言葉は、一芸に秀でるだけでなく、広範な知識と理解を持つことの重要性を示しています。孔子はまた、「政治とは、誤りを正すこと。指導者が正しくあれば、民が間違えることはない」と述べました。これは、リーダーの行動がその組織や社会の行動に大きな影響を与えるという考え方を示しています。これらの教えは、人間関係や社会生活における道徳的な指針となっています。孔子の教えは、人間の道徳性と社会秩序を重視するという点で、今日でも多くの人々に影響を与えています。
論語の基本とその教え
孔子の教えは「論語」にまとめられ、その中には孔子自身の言葉や弟子たちとの対話が記録されています。これらの教えは、個々の行動から社会全体の秩序まで、人間の生活のあらゆる側面に影響を与えています。この書物は、孔子の死後約300年後に弟子たちが編纂したもので、道徳、政治、祭礼、歴史などの各分野に関する孔子の教えを簡潔な文章で紹介しています。「論語」の中心的な教えは、「仁・義・礼・智・信」の五徳(ごとく)または五常(ごじょう)という5つの徳です。これらは人が生きる上で大切なもの、目指すべきもの、守るべきものとされています。具体的には、「仁」は思いやりの心、「義」は正義、「礼」は礼儀を忘れないこと、「智」は物事を正しく判断する知恵、「信」は信頼されるような誠実さを意味します。また、「論語」は各篇に篇名がつけられており、それぞれの篇は平均25章の短文で構成されています。各篇は特定のテーマに基づいているわけではありませんが、類似した話題が多く集まっています。「論語」の教えは、人間の道徳性と社会秩序を重視するという点で、今日でも多くの人々に影響を与えています。
孔子と老子
孔子と老子は古代中国の二大思想家で、それぞれ異なる哲学を提唱しました。孔子は儒教の創始者とされ、彼の教えは「仁」と「礼」を重視しています。「仁」は人を愛することを基本とし、「礼」は外見的な秩序を意味します。孔子は人間関係や社会生活における道徳的な指針となる教えを残しました。彼の教えは「論語」にまとめられ、その中には孔子自身の言葉や弟子たちとの対話が記録されています。一方、老子は道教の創始者とされ、彼の教えは「道」と「無為自然」を重視しています。「道」は宇宙の真理を指し、「無為自然」は自然の流れに身を任せることを意味します。老子の教えは「道徳経」にまとめられ、その中には老子自身の言葉や思想が記録されています。孔子と老子の教えは、それぞれ異なる視点から人間の生き方や社会のあり方を考察しており、その影響は今日でも多くの人々に及んでいます。孔子の教えは人間の道徳性と社会秩序を重視する一方、老子の教えは自然の流れに身を任せ、物事を無理に変えようとしないという考え方を重視しています。これらの教えは、個々の行動から社会全体の秩序まで、人間の生活のあらゆる側面に影響を与えています。
孔子の名言(1)
名言1
物事を迅速にしたいと、望んではならない。
小さな利点に目をとめてはならない。
物事を早く行うことばかり望むと、十分になすことができない。
小さな利点にとらわれると、大きな仕事が達成できない。
名言2
良心に照らして少しもやましいところがなければ、何を悩むことがあろうか。
何を恐れることがあろうか。
名言3
己達せんと欲して
人を達せしむ
名言4
止まりさえしなければ、どんなにゆっくりでも進めばよい。
名言5
人の本性はみなほとんど同じである。
違いが生じるのはそれぞれの習慣によってである。
名言6
最も賢い者と最も愚かなものだけが、決して変わることがない。
名言7
人間は逆境において人間の真価を試される。
人生の達人は逆境を楽しみ、順境もまた楽しむのです。
名言8
巧言令色鮮し仁(こうげんれいしょくすくなしじん)
名言9
三人行けば必ず我が師あり。
その善なるものをえらび、之に従い、その不全なるものはこれを改む。
名言10
成功者は必ず、その人なりの哲学をもっているものだ。
その哲学がしっかりしているからこそ、成功者の人生は揺るがないのだ。


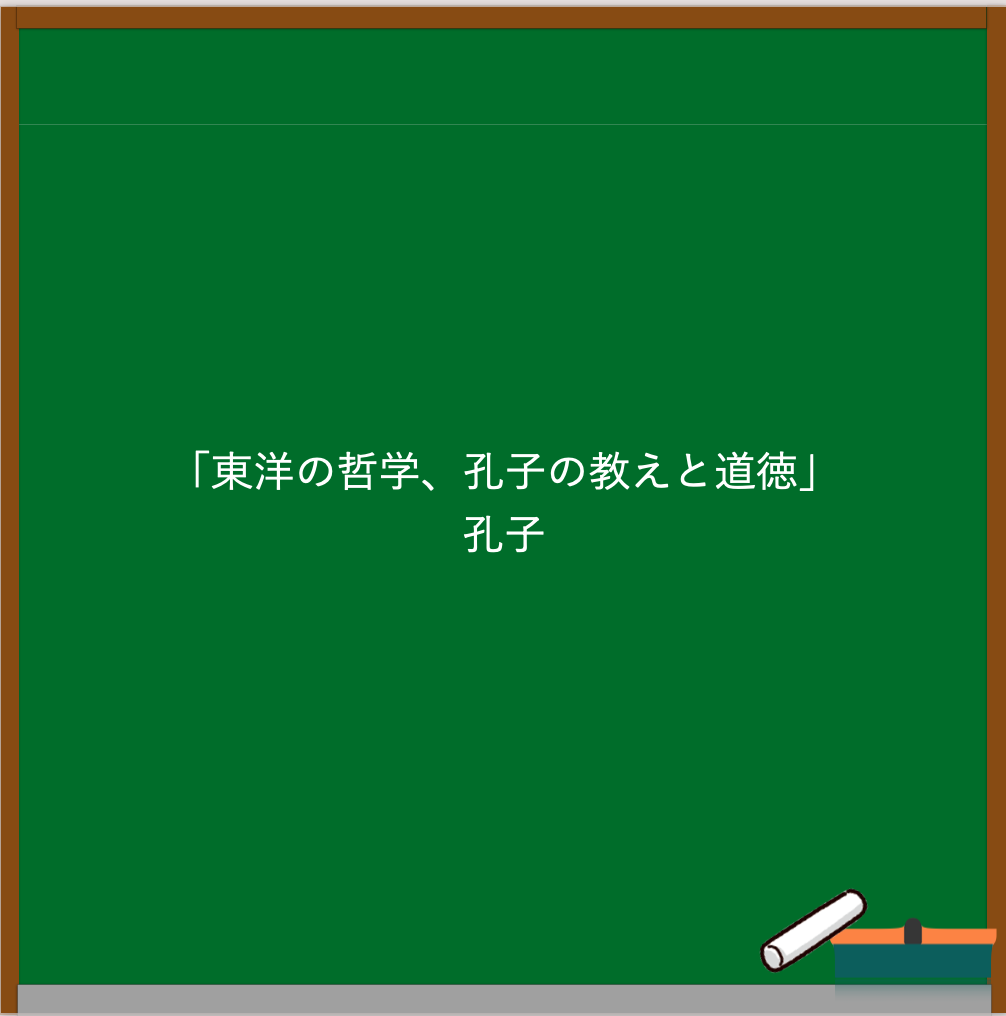


コメント