
ボブ・マーリーは、ジャマイカ音楽の世界的な認知度を高めることに貢献しました。彼はラスタファリの象徴、ジャマイカの文化とアイデンティティの世界的なシンボルともみなされました。彼の名言には、「お前は逃げる。でも、自分自身からは逃げられない。」や「飢えた群衆は、怒れる群衆なんだ。」、「ひとつのドアが閉まっている時、もっとたくさんのドアが開いているんだよ。」などがあります。
ボブ・マーリーってどんな人?
| 項目 | 情報 |
|---|---|
| フルネーム | ロバート・ネスタ・マーリー |
| 生年月日 | 1945年2月6日 |
| 出生地 | ジャマイカ、セント・アン教区、ナイン・マイルズ |
| 死亡日 | 1981年5月11日 |
| 死亡地 | アメリカ合衆国、フロリダ州、マイアミ |
| 職業 | 歌手、ギタリスト、作曲家 |
| 主な作品 | No Woman No Cry, One Love, Redemption Song, Three Little Birds, Is This Love |
ボブ・マーリーは、1945年2月6日にジャマイカのセント・アン教区のナイン・マイルズで、白人のイギリス海軍大尉の父とジャマイカ人の母との間に生まれました。彼はレゲエの先駆者の一人であり、スカの時代から活躍し、ロックステディ、レゲエの時代まで音楽界を駆け抜けました。また、洗練された歌声と宗教的・社会的な歌詞、曲で知られました。彼は60年代から80年代初頭までレゲエ音楽とカウンターカルチャーの活躍により、ジャマイカ音楽の世界的な認知度を高めることに貢献しました。音楽ソフトの推定売上枚数は世界中で7,500万枚を超え、彼の音楽と思想は後進のミュージシャンなどに影響を与えました。
ボブ・マーリーの戦争を止めた伝説
ボブ・マーリーが戦争を止めたとされる伝説は、1978年のジャマイカで起きた出来事にまつわるものです。この時期のジャマイカは、政治的な緊張が高まり、政治的暴力が日常化していました。国は二大政党、ジャマイカ労働党(JLP)と人民国民党(PNP)の間の激しい対立により、内戦状態に近い混乱に陥っていました。
ワン・ラブ・ピース・コンサート
ボブ・マーリーがこの政治的暴力のサイクルを止めるために立ち上がったのは、1978年4月22日にキングストンで開催された「ワン・ラブ・ピース・コンサート」でのことでした。このコンサートは、ジャマイカの社会的な治癒と和解を目的として企画されましたが、ボブ・マーリーはこのイベントのために、1976年の暗殺未遂事件後に避難していたイギリスからジャマイカに戻る決断をしました。
和解のジェスチャー

コンサートのクライマックスで、ボブ・マーリーは当時のジャマイカの首相マイケル・マンリー(人民国民党)と野党リーダーのエドワード・シアガ(ジャマイカ労働党)の両名をステージ上に呼び出しました。彼は二人の手を取り、高く掲げることで、国の和解と団結のシンボリックなジェスチャーを行いました。この瞬間は、多くのジャマイカ人に強い印象を与え、国の分断を超えた団結のメッセージを送りました。ボブ・マーリーのこの行動は、直接的に戦争を止めることにはなりませんでしたが、政治的暴力に対する強力な抗議の象徴となり、国の緊張を和らげるきっかけを作りました。マーリーの音楽と彼の平和へのコミットメントは、ジャマイカだけでなく世界中で多くの人々にインスピレーションを与え、社会変革の力としての音楽の可能性を示しました。
ボブ・マーリーの名言集(1)
名言1
お前は逃げる。
でも、自分自身からは逃げられない。
名言2
飢えた群衆は、怒れる群衆なんだ。
名言3
ひとつのドアが閉まっている時、もっとたくさんのドアが開いているんだよ。
名言4
誰もが自分の運命を決定する権利を持っている。
名言5
心配しなくていいんだよ。
どんな些細なことでもすべてうまくいくからさ。
名言6
雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけの奴らもいる。
名言7
誰もが、自分が望む生き方で、自分の人生を、精一杯生きていこう。
名言8
俺たちには学はないけど、インスピレーションがある。
もしも教育なんて受けていたら、とんでもない愚か者になっていたさ。
名言9
後ろ向きなやり方では、とても生きては行けないよ。
分かるかい。
前向きに進むんだ。
毎日が新しい日なんだから。
名言10
自分の生きる人生を愛せ。
自分の愛する人生を生きろ。


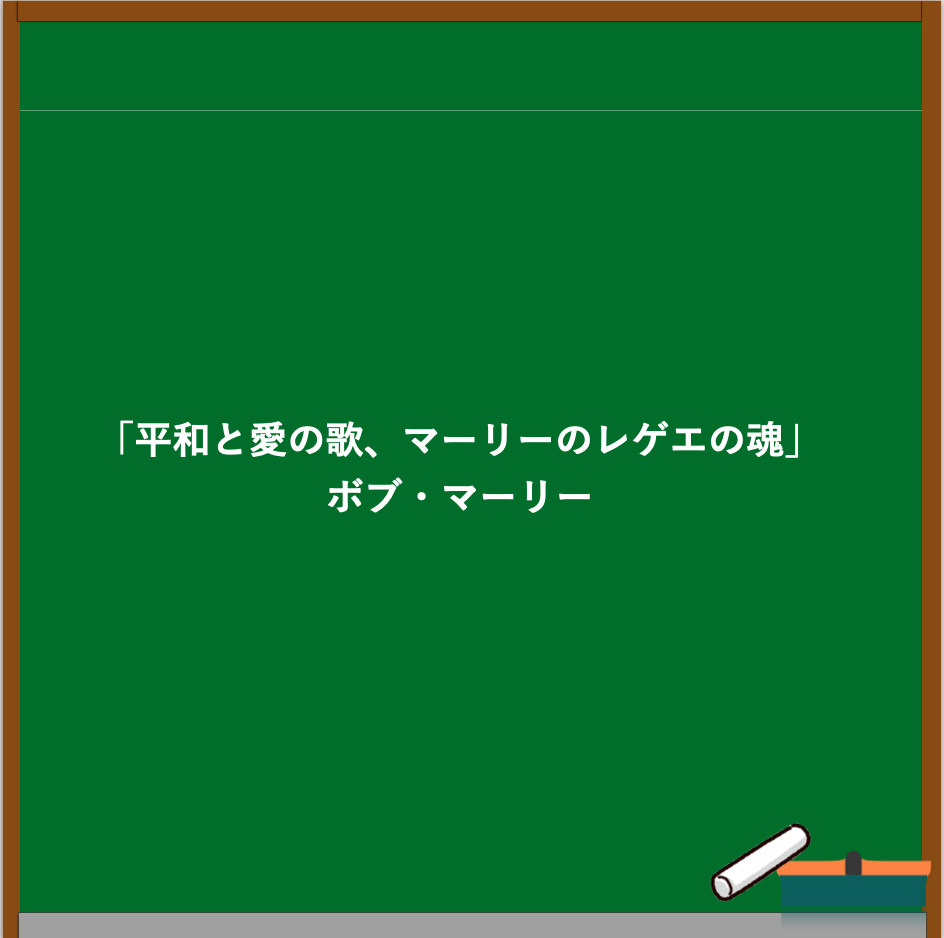


コメント