ノーベル文学賞受賞拒否など、その衝撃的な行動で知られるサルトル。彼の名言には、「人間は自らの行動の中で、自らを定義する。」、「金持ちが戦争を起こし、貧乏人が死ぬ。」、「人はサイコロと同じで、自らを人生へと投げ込む」などがあります。
人はサイコロと同じで、自らを人生へと投げ込む
サルトル 名言
サルトルの生涯
| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| 本名 | ジャン=ポール・サルトル |
| 生年月日 | 1905年6月21日 |
| 出生地 | フランス、パリ |
| 教育 | パリの高等師範学校卒業 |
| 職歴 | 教師、作家、哲学者 |
| 主な著作 | 『嘔吐』(1938年)、『存在と無』(1943年) |
| その他の業績 | 実存主義の提唱、ノーベル文学賞受賞(1964年、辞退) |
| 死去 | 1980年4月15日、パリ |
ジャン=ポール・サルトルは、1905年6月21日にフランスのパリで生まれ、彼は2歳で父を亡くし、母方の祖父に引き取られました。祖父はドイツ語の教授であり、幼いサルトルは非常に高い水準の教育を受けられましたが、一方でサルトルは3歳の頃に右目の視力をほぼ失い、以降の人生を極度の斜視として過ごすことになりました。1924年、19歳でパリの高等師範学校に入学し、生涯の伴侶となるシモーヌ・ド・ボーヴォワールと出会いました。彼らは互いに恋人を作ったり、愛人とセックスをしたりという性的な自由を見止めつつ、しかし生涯の伴侶として50年以上を連れ添うことになりました。1938年に小説作品『嘔吐』を発表して名声を得ました。彼は「実存主義」という思想を唱えたことで知られています。その後、カミュ=サルトル論争や、戦争体験に基づく左派としての活動、ノーベル文学賞の拒否などの多くのエピソードを残しました。しかし1973年ごろには両眼を完全に失明し、ほとんどの活動を制限。そして1980年、肺水腫によってサルトルは74年の生涯を閉じました。彼の葬儀にはおよそ5万人が訪れ、さながら国葬のようだったという記録が伝わっています。
サルトルの思想とその影響
サルトルは意識、あるいは人間が自らに先立って決定されているものにただ従うのではなく、自らの意味を自分の自身で規定していくことを目指したものだと言えます。そして、サルトルは、この思想を「実存主義」と呼びました。彼の思想は、特に1950年代の構造主義の台頭によってサルトルの実存主義が論破されたことにより、サルトルは過去の人というレッテルを張られ、急速にその名声を失っていった。だがサルトルの思想は現在の私たちにも影響を与えている。むしろ現在その思想は見直されているのである。インターネットでつながって、他人との比較の中で日々苦しみながら生きる現代人にとって大切な何かを教えてくれている。
ノーベル賞拒否のエピソード
ジャン=ポール・サルトルは1964年にノーベル文学賞を辞退しました。彼はスウェーデンのメディアに送ったコメントの中で、辞退はパフォーマンスでもなければ、衝動的に行ったわけでもない、と述べています。彼の長きにわたる主張に沿った行動として辞退したのだ、と主張しました。サルトルは、世界で最も権威ある文学賞を自ら辞退した唯一の人物で、1945年の仏最高勲章レジオン・ドヌールも辞退しています。後の説明では、「公的な賞はどれも辞退してきた」と述べ、その理由として独立性の制限などを挙げています。ノーベル賞をめぐっては、辞退を要請するサルトルの書簡が間に合わなかったのではないかとの憶測はあったが、今回の資料開示でその臆測が初めて裏付けられました。同紙によると、候補者として数年間名前が挙がり続けていたサルトルは、1964年10月14日にノーベル財団宛に書簡を送り、「今年も今後も」同賞を受け取ることはできないだろうと伝えているという。
サルトルの代表作ベスト3!
サルトルの代表作品ベスト3のジャンルと内容をまとめました!
嘔吐

ジャンル:実在主義
内容:1938年に出版されたこの小説は、主人公アントワーヌ・ロカンタンの日記形式で物語が展開します。30歳になったロカンタンは、彼自身が好んだ研究から愛する女性との関係、紙くずから小石に至るまであらゆるものからの正体不明の嫌悪感に苦しめられる様子とその理由についてが大筋となっています。
自由への道

ジャンル:哲学
内容:この作品は、マチウという名前の34歳の哲学教師が主人公です。彼の恋人が妊娠し、堕胎の金策に走り回るマチウ、悪の意識を研ぎ澄ます友人ダニエル、青春を疾走する姉弟の物語が描かれています。物語は第二次大戦前夜のパリでの三日間を描いています。
弁証法的理性批判

ジャンル:哲学
内容:この作品では、サルトルは初期の哲学『存在と無』における自由の哲学が深められたマルクス主義的実存哲学の中ではどのように記述されるかを『存在と無』の用語を用いて説明しています。基本的にマルクス主義の正当性を肯定しながらも、その硬直した教条主義を批判し、人間の自由を肯定する実存主義をその中へ織り込むことによって、マルクス主義に若き活力を取り戻そうとするものでした。
名言「人はサイコロと同じで、自らを人生へと投げ込む」
先ほど紹介したように、ジャン=ポール・サルトルはフランスの哲学者で、実存主義の提唱者として知られています。彼の名言「人はサイコロと同じで、自らを人生へと投げ込む」は、彼の実存主義の思想を象徴するものです。この名言は、人間の自由と選択、そしてその結果に対する責任を強調しています。サルトルは、人間が自分自身の運命を決定するためには、自分自身を未知の未来へと投げ込む必要があると考えていました。これはサイコロを振る行為に例えられます。サイコロを振るとき、その結果は完全に予測不可能で、それは人生の不確定性を象徴しています。しかし、サルトルは、この不確定性を恐れるべきではないと主張します。それどころか、この不確定性こそが人間の自由を可能にすると彼は考えていました。つまり、人間は自分自身の選択によって自分自身を定義し、その結果に対して責任を持つべきだとサルトルは説いています。
「人はサイコロと同じで、自らを人生へと投げ込む」
サルトル 名言
サルトルの名言集(1)
名言1
人間は自らの行動の中で、自らを定義する。
名言2
金持ちが戦争を起こし、貧乏人が死ぬ。
名言3
われわれの自由とは、今日、自由になるために戦う自由な選択以外のなにものでもない。
名言4
生きることと書くことを、作家は一つにすべきだ。
名言5
わたしたちは自分の愛する人を評価しない。
名言6
人生は絶望の反対側で始まる。
名言7
批評家とは、他人の思想について思考する人間である。
名言8
人は自由であることを運命づけられている。
なぜなら、いったんこの世に投げ込まれると、人は自分の行動のすべてに責任を負わなければならないからだ。
名言9
人間は、時には自由であったり時には奴隷であったりすることはできないであろう。
人間は常に全面的に自由であるか、あるいは常に全面的に自由でないか、そのいずれかである。
名言10
午後3時という時刻は、何をするにしても遅すぎるか、早すぎるのだ。


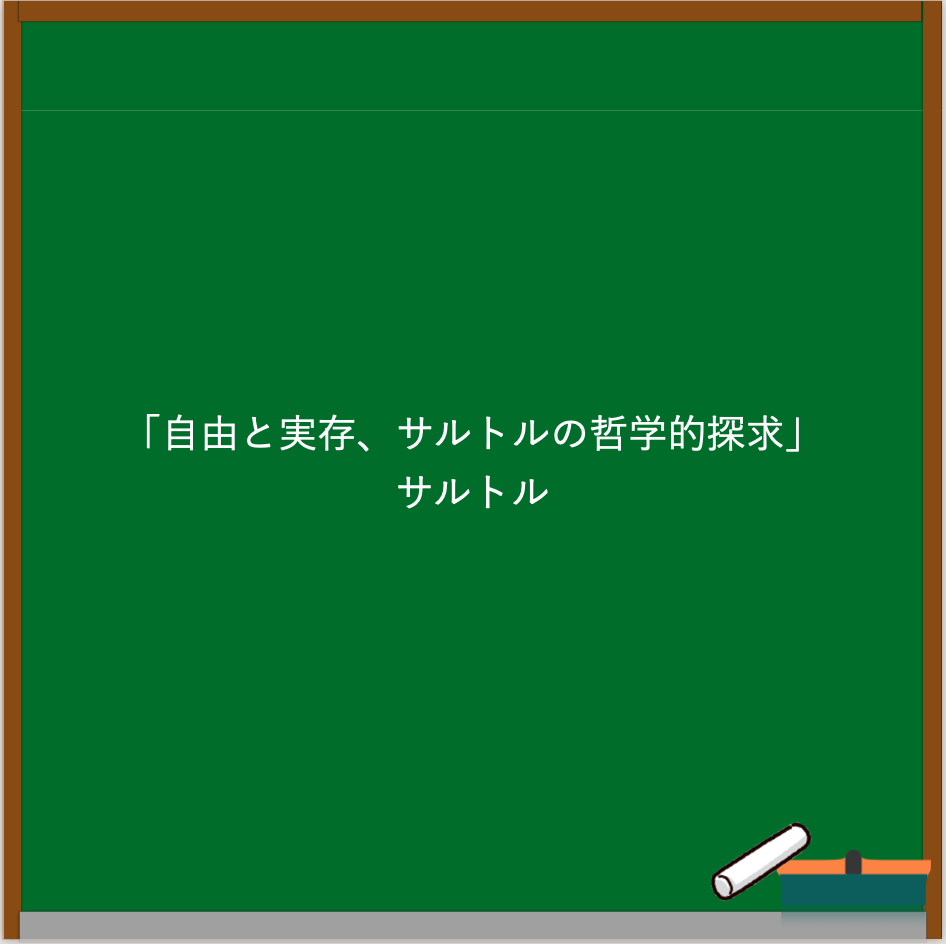


コメント