
幕末の激動の時代、一人の男が風雲急を告げる日本の歴史に名を刻みました。その名は高杉晋作。彼の生涯は短く、たった27年でしたが、その中で彼は数々の偉業を成し遂げ、日本の歴史に大きな足跡を残しました。彼の言葉は今もなお、私たちの心に深く響きます。まずは彼のかの有名な世辞の句を紹介します。
おもしろき ことをなき世を おもしろく すみなすものは 心なりけり
高杉晋作世辞の句
高杉晋作って何をした?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本名 | 春風 |
| 通称 | 晋作 |
| 生年月日 | 1838年9月27日 |
| 出身地 | 長州藩(現在の山口県) |
| 死亡日 | 1867年5月17日(27歳) |
| 主な功績 | 奇兵隊結成、脱藩、第二次長州征討への参加 |
| 死因 | 肺結核 |
高杉晋作は、幕末の激動の時代を生き抜いた、長州藩出身の志士でした。彼の本名は「春風」で、通称は「晋作」でした。彼は戦国時代から代々毛利家に仕えてきた名門、高杉家に生まれました。彼の生涯は、本名「春風」のごとく激しく、たった27年という短い人生でした。彼の人生には、長州藩一の美女との結婚や、「奇兵隊」を結成、脱藩、第二次長州征討への参加など様々な功績や武勇伝があります。討幕から大政奉還へという新しい時代を見ることなく亡くなってしまいましたが、晋作は250年以上続く幕府の権威を落とし、新しい時代の扉を開くきっかけを作った一人だと言えるでしょう。高杉晋作は1867年5月17日、肺結核によって27歳の若さで亡くなりました。彼が残した言葉からも、長州藩士らしい男気を感じ取ることが出来ます。「男子たるもの困ったという一言だけは決して口にしてはいけない」という言葉は、彼の強い意志と決断力を表しています。彼の人生は短かったですが、その中で多くの功績を残し、日本の歴史に大きな影響を与えました。そのため、高杉晋作は幕末の英雄として多くの人々に敬愛されています。
高杉晋作の生涯と時代背景
高杉晋作が生きた時代は、日本の歴史における非常に重要な転換期でした。幕末と呼ばれる時代で、江戸時代から明治時代へと移行する過渡期にあたります。この時代は、徳川幕府による封建制度の矛盾が激化し、百姓一揆が全国各地で頻発していました。また、欧米列強の侵略の波が日本に押し寄せ、幕府が屈従的な条約を結ぶという外圧も増していました。高杉晋作自身は、この激動の時代を生き抜き、尊王攘夷(倒幕派)の志士として活躍しました。彼は長州藩出身で、幕末の長州藩の尊王攘夷志士として、奇兵隊を結成して倒幕運動に大きく貢献しました。彼の活動は、幕末の風雲児とも称され、その行動力と思想は、幕末の動乱という時代背景と深く結びついています。
尊王攘夷運動とは?
尊王攘夷運動は、幕末の日本で起こった政治的な運動で、「天皇を尊敬し、外国人を日本から追い出す」という思想を持っていました。この運動は、特に西日本の雄藩である長州藩や薩摩藩で高まり、幕末の政治運動の中心となりました。尊王攘夷運動は、当時の日本が直面していた内外の危機に対応するためのものでした。1853年のペリー来航により、長く続いた鎖国政策が終わり、開国を余儀なくされた日本は、外国の圧力により不平等な条約を結ばざるを得なくなりました。これにより、日本の産業は打撃を受け、外国人による犯罪も増え、日本人の反発を招きました。このような状況下で、尊王攘夷運動は、「天皇を尊敬し、外国人を日本から追い出す」という思想を掲げ、国民の支持を集めました。その後の結果としては、尊王攘夷運動は、日本の政治体制の大きな変革をもたらしました。当初は外国との力の差を知り、攘夷は不可能と考えた人々も多かったですが、幕府が外国の圧力に屈するばかりで頼りにならないと感じた薩摩藩や長州藩は、攘夷をやめ、幕府を倒して天皇中心の政治体制をつくる「尊王倒幕」に路線変更しました。これにより、倒幕の動きは加速し、最終的には江戸幕府の消滅と明治維新を実現しました。
高杉晋作と奇兵隊
高杉晋作は、1863年に下関で外国船に対する砲撃後、兵士が不足している状況を解消するために奇兵隊を結成しました。奇兵隊は武士だけでなく庶民も参加し、西洋式の戦術と兵器を用いて下関沿岸を防御しました。しかし、隊員が武士を斬りつける事件が発生し、高杉は一度奇兵隊の総監を解任されました。その後、長州藩が幕府に敗北すると高杉は復帰し、幕府軍を撤退させることに成功しました。高杉亡き後も奇兵隊は活躍しましたが、明治時代になり戦がなくなると解散しました。
吉田松陰の元で学ぶ
高杉晋作は1839年に長州藩の上級武士である父・小忠太と母・ミチの長男として生まれました。幼少期から負けん気が強く、剣術に熱心でした。10歳の時には天然痘を患いましたが、家族の献身的な看護で一命を取り留めました。その後、藩校の明倫館に入学し、剣術などを学びました。18歳になると、吉田松陰の主宰する松下村塾に入学し、「草莽崛起」という思想に感銘を受けました。これらの経験が、後の彼の活動に大きな影響を与えました。
高杉晋作の死因と世辞の句
高杉晋作は、幕末の長州藩の尊王攘夷志士として活躍しましたが、明治維新を目前にして結核に倒れ、29歳の若さで亡くなりました。彼の死因は結核による病死でした。1866年の第二次長州征伐で長州藩が幕府軍に勝利した後、体調を崩しました。その後、療養に努めましたが、回復することはありませんでした。1867年5月17日、大政奉還から半年ほど前に、高杉晋作はこの世を去りました。高杉晋作が残した最後の言葉として有名なものが二つあります。一つは、「三千世界の鴉を殺して主と朝寝がしてみたい」というものです。これは、高杉晋作が遊女に宛てたものとされています。「三千世界」とは仏教用語でこの世界すべてを意味し、「鴉」は朝を知らせる鳥です。もう一つは、「おもしろき事もなき世をおもしろく、すみなすものは心なりけり」というものです。これは、「世の中に面白いことがなくても、自分次第で面白くできる」という意味であり、高杉晋作の人生観や思想を示したものです。この言葉は、高杉晋作自身が詠んだ上の句と、女流歌人の野村望東尼が詠んだ下の句から成り立っています。
高杉晋作の名言集(1)
名言1
シャクトリムシのように身を屈するのも、いずれは龍のように伸びるためだ。
そのためには、奴隷になっても、下僕になっても構わない。
名言2
太閤も天保弘化に生まれなば、何も得せずに死ぬべかりけり。
名言3
友人の信頼の度合いは人の死や緊急事態、困難の状況の時に分かる。
名言4
真の楽しみは苦しみの中にこそある。
名言5
今さらに
なにをかいわむ
遅桜
故郷の風に
散るぞうれしき
先生を
慕うてようやく
野山獄
名言6
死後に墓前にて
芸妓御集め
三弦など御鳴らし
御祭りくだされ
名言7
戦いは一日早ければ一日の利益がある。
まず飛びだすことだ。
思案はそれからでいい。
名言8
死だなら
釈迦と孔子に追いついて
道の奥義を
尋ねんとこそ思へ
名言9
苦しいという言葉だけはどんなことがあっても言わないでおこうじゃないか。
名言10
古くから天下のことを行う者は、大義を本分とし、決して他人に左右されることなく、断固として志を貫く。
禍福や死生によって気持ちが揺れ動いたりするものではない。


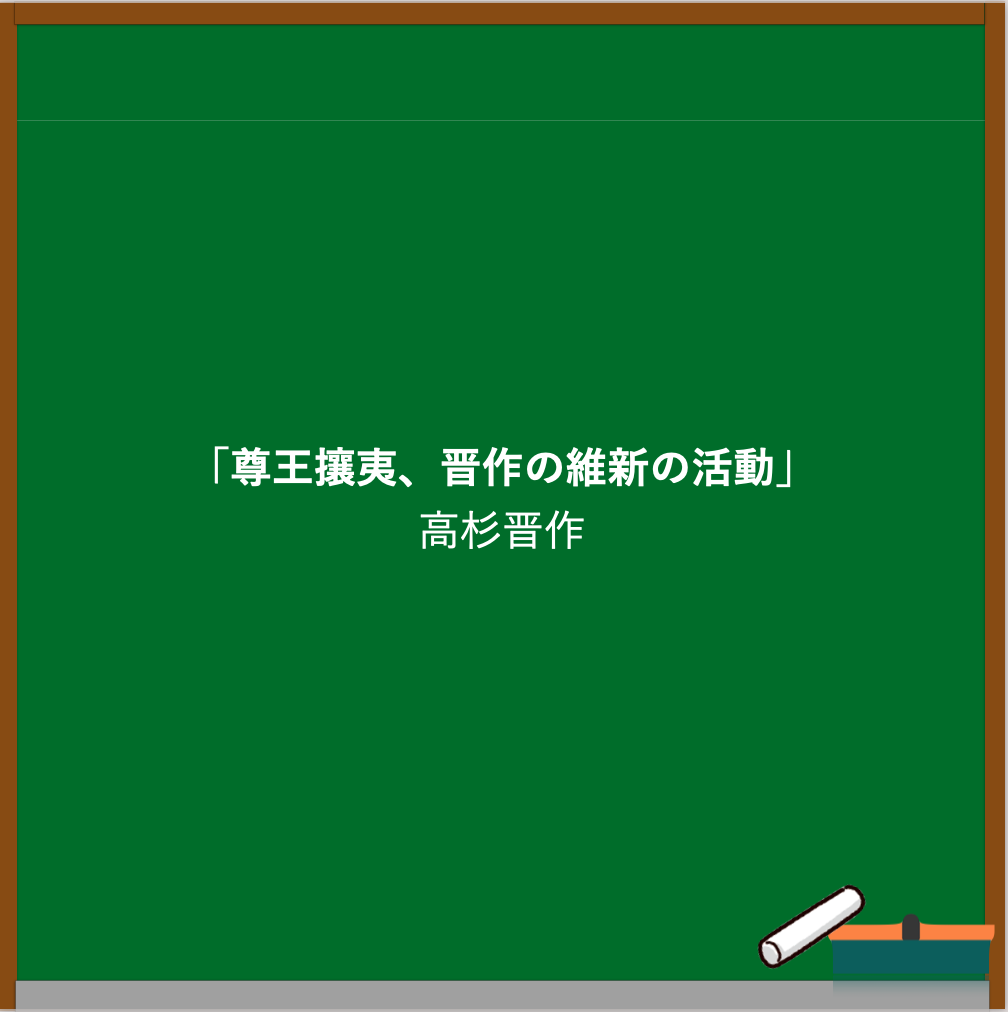


コメント