
本田宗一郎は、ホンダを創設し、世界的な大企業に育て上げた男です。彼の名言は、彼が持っていた情熱、創造性、そして不屈の精神を反映しています。彼の名言には、「創業当時、私が「世界的視野に立ってものを考えよう」と言ったら噴き出した奴がいた。」、「会社の為に働くな。自分が犠牲になるつもりで勤めたり、物を作ったりする人間がいるはずない。だから、会社の為などと言わず、自分の為に働け。」、「人を動かすことのできる人は他人の気持ちになれる人である」などがあります。
本田宗一郎の人生
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 生年月日 | 1906年11月17日 |
| 出身地 | 静岡県浜松市天竜区 |
| 主な業績 | Hondaの創業、F1優勝 |
| 死去 | 1991年8月5日 |
| 死因 | 肝不全 |
本田宗一郎は、1906年11月17日に静岡県浜松市天竜区で生まれました。彼の父親は鍛冶屋で、幼少期から機械に興味を持つようになりました。彼が初めて自動車を目にしたのは、小学校在学中のことでした。彼は高等小学校を卒業後、自動車修理工場「アート商会」に入社しその後、30歳で東海精機重工業株式会社の社長に就任しましたが、戦争の影響で会社を引き払うことを余儀なくされました。1946年、本田は本田技術研究所を設立しました。初期はバイクの制作に力を入れていましたが、会社が大きくなるにつれて自動車産業にも乗り出していきました。彼の功績は数多く、特に1964年のドイツGPでF1初挑戦を果たし、翌年には初優勝を飾るなど、モータースポーツでも活躍を見せました。また、彼は部下の育成にも力を入れていました。彼は部下に対し、「よくやった」と褒めることはほとんどなかったそうです。仕事が目標としていた領域に達したとしても、「限界までやったのか?」とよく聞き返しました。本田宗一郎は1991年8月5日に肝不全で亡くなりました。享年84歳でした。彼の遺志は今も引き継がれ、本田技研工業(通称:ホンダ)は現在でも世界的な大企業として存在感を放っています。
本田宗一郎の功績やエピソード
本田宗一郎のエピソードや功績をまとめました。名言と合わせてエピソードをお読みください。
機械が大好きな幼少期
本田宗一郎は幼少期から機械いじりに夢中で、自由奔放な性格で、ただ無責任に行動するのではなく人に迷惑をかけることを嫌い、約束の時間は絶対に守る几帳面さも持ち合わせていました。彼が自動車好きになったきっかけは、村に初めて自動車がやってきた時です。本田宗一郎は目の前を走る黒く輝くセダンを見て「これが、自動車か」と、自動車の後ろを掴みながら一緒に走りました。15歳で東京・本郷の自動車修理会社「アート商会」に丁稚奉公に出ました。アート商会では、仕事といえば掃除や子守りばかりさせられていましたが、本田宗一郎は「自動車を近くで見られるだけで幸せなんだ」と自身を鼓舞して雑用をこなしていきました。大正12年(1923年)の関東大震災が起こった時、本田宗一郎は自動車を生まれて初めて運転しました。本田宗一郎は自動車を運転することに感動と興奮を覚え、地震など気にならなかったと語っています。
バタバタの開発秘話
本田宗一郎が開発した「バタバタ」は、ホンダのバイク開発の起源とも言える製品です。1946年、本田宗一郎は自転車に取り付ける補助エンジンの生産を思いつき、自転車に取り付けられたエンジンを作りました。このエンジン付き自転車は大人気となり、爆音のうるささから「バタバタ」と呼ばれるようになりました。その後、「バタバタ」は商品として大成功を収め、これが本田技研工業のスタートでもあり、その後のホンダのバイク開発の基礎となりました。2023年、ホンダは自転車に取り付ける電動アシストユニットと、それに連動するスマートフォンアプリを開発しました。これにより、様々な自転車を電動アシスト化・コネクテッド化できるサービス「SmaChari」が誕生しました。これは、現代版「バタバタ」とも言える製品で、本田宗一郎の「バタバタ」の精神を受け継いでいます。
F1への挑戦「世界一じゃないと意味がない」
本田宗一郎が率いるホンダがF1に初めて参戦したのは1964年で、その背後には彼の強い意志と情熱がありました。1964年1月、ホンダはF1レースへの出場を宣言しました。この宣言から6年間のF1参戦期間を第一期と呼ばれています。オートバイのマン島TTレースで完全優勝を成し遂げた時から、次は4輪かなと、だれもが感じていました。そして、自分たちの技術をもってすれば必ず勝てる、という勢いが研究所にはあったのです。本田宗一郎は、「私の幼き頃よりの夢は、自分で製作した自動車で全世界の自動車競争の覇者となることであった」という強い意志を持っていました。この想いが、ホンダがF1に参戦する原動力となりました。ホンダF1第一期はシーズンで優勝2回、2位1回、3位2回の記録を残しました。その後期間を空けますが、アイルトン・セナの黄金期を支えたマクラーレン時代のF1第二期や、マックス・フェルスタッペンの大記録を現在継続して支えている第四期に繋がっていきます。
アイルトン・セナとの関係
本田宗一郎とアイルトン・セナの間には、数々の感動的なエピソードが存在します。1988年10月、F1鈴鹿グランプリで優勝したアイルトン・セナは、本田宗一郎と肩を組み、喜びを分かち合いました。レース後、ホンダブースで行われた祝勝会で、82歳の本田氏は孫のような28歳のセナを思い切り抱き締めました。本田氏は「やっとF1が自分のものになった」と体を震わせました。本田宗一郎はセナに対して、「お前のために最高のエンジンを作ってやるよ」と約束しました。これに感動したセナは、「本田さんは日本での父」と感じ、その後もホンダエンジンを愛用し続けました。1990年のFIA表彰式で特別功労賞を受けた本田宗一郎は、セナに「セナ君、おめでとう。来年も、ナンバーワンのエンジン、作るよ」と言いました。これに感極まったセナは涙を流しました。
名言「99%の失敗に支えられた1%」
ホンダは失敗の集大成とまでと言われている企業ですが、そんなホンダはどのような失敗をしてきたのでしょうか?ホンダの失敗の数々を紹介します。
- ホンダ1300の失敗: 本田宗一郎の信念により空冷エンジンを搭載したホンダ1300は、商品としては失敗に終わりました。しかし、この苦い経験は後のシビックやアコードの開発に生かされました。
- F1での空冷エンジンの失敗: ホンダはF1に参戦し、空冷V型8気筒という常識破りのマシンも製作しましたが、これも成功とは言えませんでした。
- 初の小型乗用車の失敗: ホンダ初の小型乗用車(FF)のホンダ1300は、本田宗一郎の信念により空冷エンジンを搭載しましたが、うまくいきませんでした。
これらの失敗は、本田宗一郎とホンダにとって、新たな成功への道しるべとなりました。本田宗一郎は、「失敗からしか行けない道がある」と語り、その精神はホンダのDNAとして受け継がれています。成功は誰でもするとは限らないが、失敗なら誰もがする。それが本田宗一郎の言葉の背景にあるエピソードです。
成功は誰でもするとは限らないが、失敗なら誰もがする。多くの人々は皆成功を夢見、望んでいるが、成功とは99%の失敗に支えられた1%だと考える。
https://kabushikihakushi.com/2023/09/16/honda_soichiro_quotes-page-1/
経営哲学「会社のために働くな」
本田宗一郎の「会社のために働くな」という発言は、彼の経営哲学を象徴するもので、自己実現と個人の成長を重視する考え方を示しています。本田宗一郎は、社員が会社のために働くという考え方を否定し、自分自身のために働くことを強調しました。彼は、社員が自分自身のために働くことが、結果的に会社にとってもプラスになり、会社をよくすると考えていました。また、彼は「会社だけよくなって、自分が犠牲になるなんて、そんな昔の軍隊のようなことを私は要求していない」と述べています。彼のこの発言は、自分自身のために働くこと、つまり自分自身の成長と自己実現を追求することが、結果的には会社の成長につながるという考え方を示しています。これは、個々の社員の成長と自己実現が、組織全体の成長にとって重要であるという本田宗一郎の経営哲学を表しています。
会社の為に働くな。自分が犠牲になるつもりで勤めたり、物を作ったりする人間がいるはずない。だから、会社の為などと言わず、自分の為に働け。
本田宗一郎著 「会社のために働くな」 PHP研究所
名言「人を動かす」ことについて
本田宗一郎その革新的なビジネス戦略とリーダーシップで世界的に成功を収めましたが、この名言はリーダーシップや人間関係における共感の重要性を強調しています。一人では決して成功できない、人を動かすことができる能力の重要性を説いています。本田宗一郎のこの名言に類似する名言を次に紹介していきます。
人を動かすことのできる人は他人の気持ちになれる人である
本田宗一郎 名言 人を動かす
人を動かす名言
スティーヴン・R・コヴィー:コヴィーは、『7つの習慣』の著者として知られ、効果的な人間関係を築くためには共感が不可欠であると述べています。共感を持つことで、他人を理解し、より良い関係を築くことができるとしています。
「共感は人間関係の糸口であり、他人を理解するための第一歩である。」
スティーヴン・R・コヴィー 名言
デール・カーネギー:カーネギーは、自己啓発書『人を動かす』の著者であり、他人の気持ちを理解し、共感を示すことが、人間関係を良好に保ち、他人を動かすための鍵であると強調しています。
「人を動かすための最も強力な武器は、他人に対する理解と共感である。」
デール・カーネギー 名言
ジェフリー・フェファー:スタンフォード大学の経営学教授であるフェファーは、リーダーシップにおける共感の重要性を説き、他人の視点を理解しようとすることが、リーダーシップの本質であると述べています。
「本当に大きな力を持つリーダーは、他人の視点から物事を見ることができる人である。」
ジェフリー・フェファー 名言
本田宗一郎の名言集(1)
名言1
創業当時、私が「世界的視野に立ってものを考えよう」と言ったら噴き出した奴がいた。
名言2
会社の為に働くな。
自分が犠牲になるつもりで勤めたり、物を作ったりする人間がいるはずない。
だから、会社の為などと言わず、自分の為に働け。
名言3
私は自分と同じ性格の人間とは組まないという信念を持っていた。
名言4
成功者は、例え不運な事態に見舞われても、この試練を乗り越えたら、必ず成功すると考えている。
そして、最後まで諦めなかった人間が成功しているのである。
名言5
もったいないようだけど、捨てることが、一番巧妙な方法だね。
捨てることを惜しんでいるヤツは、いつまでたってもできないね。
名言6
人生でも、企業でも、一度貧乏とか不況とかを立派にくぐり抜いてきたものなら、そいつはどこまでも信用できる。
名言7
新しい発想を得ようと思うならまず誰かに話を聞け。
名言8
進歩とは反省の厳しさに正比例する。
名言9
需要がそこにあるのではない。
我々が需要を作り出すのだ。
名言10
自分の力の足りなさを自覚し、知恵や力を貸してくれる他人の存在を知るのもいい経験である。


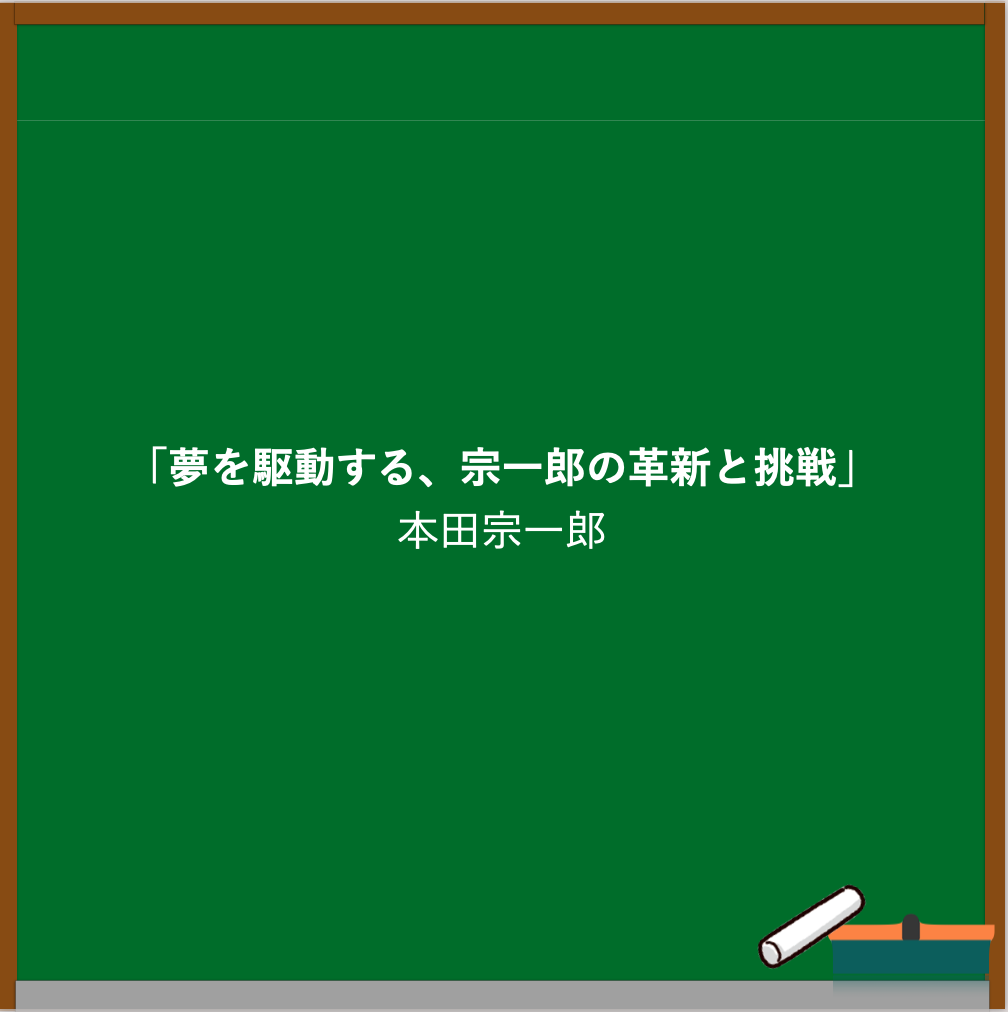


コメント